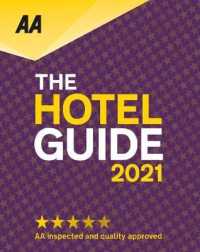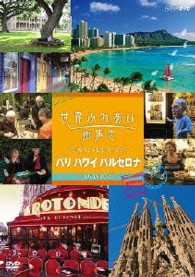出版社内容情報
systemd(システムディー)はLinuxの基本的な構成要素を提供するソフトウェア群です。システムやサービスの管理機能を中心として、ハードウェアの管理、ログの管理などを行う多数の独立したソフトウェアからなっています。
Linuxでシステム管理を行うときにはsystemdの知識が必要になります。systemdに関するオンラインマニュアルなどは充実しているものの、systemdがどんな機能を提供しているかを知らなければ「どのドキュメントを読めばいいのか」「何を探すべきなのか」の見当がつかないでしょう。
本書はsystemdの概要をつかみ、マニュアルなどを適切に参照できるようになることを目的としています。systemdの設定変更や、設定ファイル(unit file)の解釈/作成/変更、systemdが記録したログの読解などのシーンで役立つトピックを解説します。また、systemdの機能に対応するLinuxカーネルの機能を知ることができます。Red Hat Enterprise Linux 8と9を題材にして解説しますが、多くの内容は他のディストリビューション(Debian、Ubuntu、openSUSEなど)でも活用できます。
※本書は雑誌『Software Design』の2021年6月号~2022年11月号に掲載された連載記事「systemd詳解」を再編集した書籍です。
内容説明
serviceがactiveになるタイミングはいつ?systemd‐journaldがローテートする基準は何?日常の作業に必要な最低限の知識よりも一歩踏み込んだ話題を解説。systemdの概観をつかめるほか、よくあるトラブルや疑問も扱います。Red Hat Enterprise Linux 8と9を題材にしていますが、多くの内容は他のディストリビューション(Debian、Ubuntu、openSUSEなど)でも活用できます。
目次
第1章 systemdとは
第2章 unitとunit file
第3章 unitの状態、unit間の依存関係、target unit
第4章 プロセス実行環境の用意
第5章 service unit
第6章 timer/path/socket unit
第7章 generatorとmount/automount/swap unit
第8章 control group、slice unit、scope unit
第9章 udev、device unit
第10章 systemd‐journald
第11章 core dump管理
第12章 systemd‐logind、pam_systemd
第13章 systemd‐tmpfiles、systemd‐sysusers
第14章 D‐Busとpolkit
第15章 systemd‐resolved
第16章 systemdのその他の機能
著者等紹介
森若和雄[モリワカカズオ]
レッドハット株式会社所属(2023年10月現在)の自称RHELおじさん。1976年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mft
やご
Q
shinki_uei
しょっさん
-
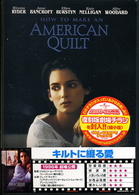
- DVD
- キルトに綴る愛