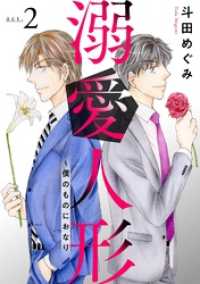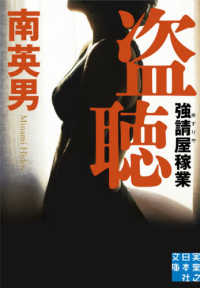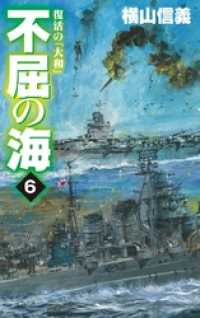出版社内容情報
魅惑的な古生物たちの世界。
知的好奇心をくすぐり、知的探究心を呼び起こし、そして何よりシンプルに面白い。
そんな世界を、みなさまにお届けします。
新シリーズ1作めは「水際における古生物の興亡」をお届けします。
陸圏と水圏の境界域にあたる“水際の世界“は、地球生命が最も躍動的に物語が紡がれた舞台の一つ。
かつて水の中で生まれた私たちの祖先は、水際世界への“上陸作戦”を展開し、新天地たる陸域へ生活圏を拡大しました。
一方、陸域で繁栄を遂げた生物の中から、再び水際世界へ侵食し、水の中に“逆進出“を遂げるものが出現します。
彼らは“水際の世界”を、時に通過点とし、時に支配圏としながら、命を繋いできました。
本書は、そんな水際世界を“進化の舞台”として興亡を繰り広げた脊椎動物の3グループに焦点を当てました。
「両生類」「偽鰐類」「哺乳類」
これら3グループを中心に展開する“水際の世界”では、どんな興亡が繰り広げられたのでしょう。
地球生命を語る上で欠かせない“水際の生物史”を、存分にお楽しみください。
目次
第1章 陸へ(上陸、そして内陸へ;41億8000万年間のプロローグ ほか)
第2章 先行する両生類(栄え始めた四足動物;両生類、覇権をとる ほか)
第3章 王者登場(新時代の始まり;再び三畳紀 ほか)
第4章 水際の覇者とその仲間たち(水の世界へ;恐竜たちの“ライバル” ほか)
第5章 私たちも海へ(かくして哺乳類も水中へ進出する;さあ、水中へ。みんな、水中へ ほか)
著者等紹介
土屋健[ツチヤケン]
サイエンスライター。オフィスジオパレオント代表。日本地質学会員、日本古生物学会員、日本文藝家協会員。埼玉県出身。金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て、現職。古生物に関わる著作多数。2019年にサイエンスライターとしてはじめて古生物学会貢献賞を受賞
松本涼子[マツモトリョウコ]
神奈川県立生命の星・地球博物館、学芸員。英国ロンドン大学(University College London)にて博士号(Ph.D.)取得。専門は絶滅水生爬虫類、コリストデラ類の形態進化。近年では、現生両生類の頭骨や頸椎の形と運動機能の進化をテーマとした研究もおこなっている
小林快次[コバヤシヨシツグ]
北海道大学総合博物館、副館長・教授。大阪大学総合学術博物館、招聘教授。1971年、福井県福井市生まれ。米国ワイオミング大学卒業後、米国サザンメソジスト大学にて日本人としてはじめて恐竜で博士号を取得。国内だけではなくモンゴルや米国アラスカ、カナダなどで発掘調査を精力的におこなう世界を代表する恐竜研究者。獣脚類恐竜を中心に恐竜の分類や生態について研究をおこなっている。最近では、北海道のカムイサウルスや兵庫県のヤマトサウルスを命名した
田中嘉寛[タナカヨシヒロ]
大阪市立自然史博物館、学芸員。北海道大学総合博物館資料部・研究員を兼ねる。ニュージーランド、オタゴ大学で初期のイルカの進化を研究し博士号(Ph.D.)を取得。専門はイルカやクジラ、アシカ、アザラシ、セイウチなど、水生哺乳類の進化(古生物学)、および博物館学
かわさきしゅんいち[カワサキシュンイチ]
動物画家・絵本作家・漫画家。1990年大阪生まれ。脱サラ後、絵本『うみがめぐり』を日本・中国の2カ国で出版(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
jackbdc
5〇5
よしあ
櫛橋光