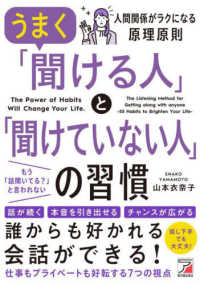出版社内容情報
ジェネラティブアートなどプログラミングで創る芸術作品が注目を集める昨今です。本書では実際にジェネラティブアート作品を作成しながら、その発想の元となる、さまざまな数学の知識と視覚表現について学んでいきます。本書を読めばきっと、数学の知識を巧みに駆使した視覚表現の多様さに驚き、魅了されることでしょう。数学の美術的側面をコンピューターを使って体感したい方、また、これまでアートに取り組んだことのないプログラマーの方にも、おすすめです。【章項目】第1章 ユークリッド互除法/第2章 連分数/第3章 フィボナッチ数列/第4章 対数らせん/第5章 フェルマーらせん/第6章 合同な数/第7章 セルオートマトン/第8章 行列の織りなす模様/第9章 正多角形の対称性/第10章 正多角形によるタイリング/第11章 正則タイリングの変形/第12章 周期性と対称性を持つ模様/第13章 周期タイリング/第14章 準周期タイリング
著者等紹介
巴山竜来[ハヤマタツキ]
専修大学経営学部准教授。博士(理学)。専門は数学(とくに複素幾何学)、および数学に関する視覚表現の実践。1982年奈良県生まれ。2010年大阪大学大学院修了後、パリ大学、国立台湾大学、清華大学でのポスドク研究員等を経て現職。2016年より雑誌『数理科学』(サイエンス社)の表紙CGを担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
20
画像アルゴリズムで幾何学模様を描く入門書。プログラミング自体も初歩から解説している。眺めるだけでもそれなりに面白いけど、やはり自分でも実装してみたくなる。Proccesingという言語は今回初めて知った。小中学生のプログラミング授業もこのようなものも取り入れてほしい。2021/07/06
Tenouji
12
コロナ禍の中で、ソースコードという原点に戻る。Processingだけどw。ベースはJava。独特の動きをするので面白い。音楽とも連動できる。フェルマー螺旋と連分数との関係。やはり、無理数は周期性がほとんどない数字なんだ、ということが視覚でわかる。新しい世界をのぞくことができたw。2020/06/10
pn675
4
数学的背景がしっかり書いてあるため、明確で分かりやすい。見るだけでも充分面白いが、自分で描いてみるとより理解できるだろう。以前から、再帰的でないペンローズタイリングの描画アルゴリズムを考えているので参考にしてみようと思う。2019/11/29
Mariyudu
2
以前読んだジェネラティブアートの本に比べて足が地についている印象。いかにもクールな「出来上がり図」を並べ立てて悦に入るのではなく、数学の不思議と面白さをビジュアライズで示しながら発想の芽をじっくり育む、という感じかしら。地味を承知でファブリケーションやタイリング等のインダストリアルな方面を取り上げるあたりも、硬派で好み。2019/11/04
p-nix
1
解説が驚くほどに丁寧で分かりやすい。具体的事例(プログラム)と数学の抽象的解説のバランスが素晴らしい2019/05/06
-
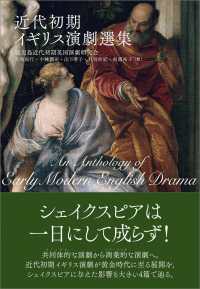
- 和書
- 近代初期イギリス演劇選集
-
 文春文庫](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0473362.jpg)
- 電子書籍
- 鬼平犯科帳[決定版](二十一) 文春文庫