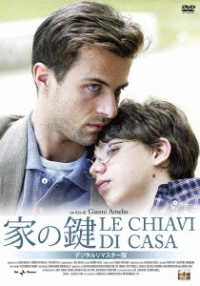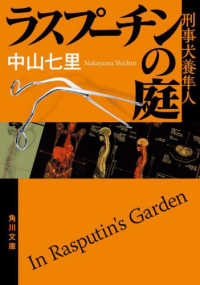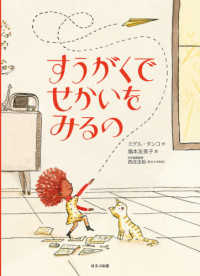出版社内容情報
●「聴く」ことは仕事を推し進めること
相手の話をじっくり聞くことで相互の理解が深まるという「傾聴」。実際、心理的安全性を高めることで相手が話しやすくなるなど、コミュニケーションが改善する効果がある。
そういった「カウンセリング」的傾聴術から、本書では一歩進めて「ビジネスを前に進める」ことを意識する。「聴く」ことによって、話を自分の思う方向に仕向ける「アサーティブ」なコミュニケーションも可能になるという。
著者は数多くのビジネスコミュニケーション研修で、傾聴が仕事に役立つことを説いてきた。カウンセラーの視点で書かれている本が多い中、本書ではビジネス現場の視点から基本を語る。
●アンガーマネジメントやアサーティブ・コミュニケーションの視点も必要
純粋に「聴く」というのは意外と難しく、様々な感情が巻き起こってきて口を挟みたくなる状況が何度となく生じる。そのときにいかにフラットな気持ちで話を聴けるか。解決策としてアンガーマネジメントで学んだ「6秒待つ」「メモをとる」ということが活きてくるという。また、日頃からバイアスを取り除く訓練も必要だ。
一方で、アクティブに聴くには相手から話を引き出す「質問する力」も必要だ。質問することでコミュニケーションのイニシアティブを取り、仕事を思うようにコントロールすることも可能となる。
本書では、リモートワーク時や集団的コミュニケーションなどのシーンを含めて、様々な事例を盛り込んで解説する。
内容説明
「伝わるコミュニケーション」をテーマに数多くの研修・講演を行う著者が、聴くことの効用を丁寧に解説します。「即座にアドバイスしない」「沈黙を怖がらない」「わかりにくい質問には、整理しながら返答する」など、具体的な手法が満載。著者の研修現場からの実例などをもとに、ケースごとに対応策を伝授します。部下が抱えている悩みに十分に耳を傾けられていないと実感しているマネジメント層や、自分の意見を主張することでいつも衝突してしまう人など、コミュニケーションに悩みを抱えるすべての人を対象にした一冊です。
目次
第1章 アクティブ・リスニングとは何か(なぜいま「傾聴力」が求められるのか;コミュニケーションは、聴き手が主導権を握るもの;コミュニケーションで目指す「聴くこと」のゴールとは?;プライベートでも、聴く力は求められる;聴く力があると、相手のSOSに気づけるようになる;聴く力は、話す力の土台になる;聴く力は自分を育てる近道;聴ける人は好かれる人でもある;話を聴ける職場が、心理的安全性のある職場になっていく;意図的な無視は、ハラスメントにあたる)
第2章 アクティブ・リスニングの基本(相手が話しやすい態度を心がける;話し手に好かれる相槌と嫌われる相槌の違い;「共感しているフリ」になっていないか;相手の話に関心を持って聴く;共通の話題がなくても、傾聴することで会話は弾む;先入観を持たずに聴く;自分の意見は横に置いて聴く;即座にアドバイスしない;沈黙を怖がらない;相談事に対して「これ以上は無理だ」と思ったら、一度リセットしてもいい)
第3章 アクティブ・リスニングの実践(観察しながら聴く;傾聴の先に要約力がある ほか)
第4章 仕事の現場でアクティブ・リスニングを活かす(立場が違う相手と、うまくコミュニケーションをとるには?;ネガティブな報告にこそ耳を傾ける ほか)
第5章 プライベートの場で活用するアクティブ・リスニング(親密な関係だからこそ、「思い込み」にとらわれずに聴く;あまり親しくない相手と、距離を縮めたいとき ほか)
著者等紹介
戸田久実[トダクミ]
アドット・コミュニケーション株式会社代表取締役。一般社団法人日本アンガーマネジメント協会理事。アンガーマネジメントコンサルタント。一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー。立教大学卒業後、株式会社服部セイコー(現・セイコーグループ株式会社)勤務を経て研修講師に。銀行・生保・製薬・通信・総合商社など大手民間企業や官公庁で「伝わるコミュニケーション」をテーマに研修や講演を実施。1on1のコンサルにも対応し、対象は新入社員から管理職、役員まで幅広い。講師歴は30年(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
羊男
権之助
ちえぞう
zozomu
hinotake0117