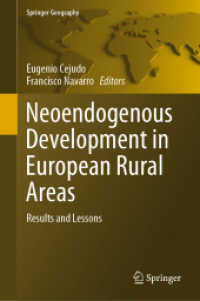- ホーム
- > 和書
- > ビジネス
- > マネープラン
- > 退職金・年金・iDeCo
出版社内容情報
1億円の老後資金があっても、取り崩し方でつまずくと、一気にピンチに?
「毎月5万円の引き出しはなぜキケン?」
「取り崩しは「額」ではなく「率」で考える」
「65~80歳、80~100歳に分けて考える」
「話題の新NISA、定年後はこう取り入れる」
誰も教えてくれなかった「リタイア後の資産の活用法」を、運用会社で長年投資教育を行ってきた著者が詳説する。
どうすれば手持ちの資産を安全に取り崩しながら充実したセカンドライフを送れるか――今日から取り入れられる具体的なアドバイスが満載。
内容説明
今ある資産を有効に使っていくために必要なのは、「資産を取り崩しながら、同時にその寿命を伸ばしていく」包括的なアプローチ、すなわち「資産活用」の技術です。その中にはもちろん、資産の潜在的な力を引き出すための資産運用も含まれます。本書では、その基本的な考え方を紹介します。
目次
序章 資産形成を終えた人に
第1章 「資産活用」世代の実態
第2章 リタイアメント・インカムとは?
第3章 「毎月10万円の引き出し」はなぜキケンなのか
第4章 引き出しは「率」で考える
第5章 保有する資産全体のなかで取り崩しを考える
第6章 資産活用層は新NISAをどう使う?
第7章 生活スタイルと資産活用
第8章 資産活用層の社会貢献
著者等紹介
野尻哲史[ノジリサトシ]
合同会社フィンウェル研究所代表。1959年生まれ。一橋大学商学部卒。82年山一証券経済研究所、同ニューヨーク事務所駐在、98年メリルリンチ証券東京支店調査部、同調査部副部長、2006年フィデリティ投信入社、07年フィデリティ退職・投資教育研究所所長。19年5月、定年を機に合同会社フィンウェル研究所を設立し、資産形成を終えた世代向けに資産の取り崩し、地方都市移住、勤労の継続などに特化した啓発活動をスタート、18年9月より金融審議会市場ワーキング・グループ委員、22年9月より同審議会顧客本位タスクフォース委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さくらっこ
スリカータ
じょうこ
*takahiro✩
ほよじー