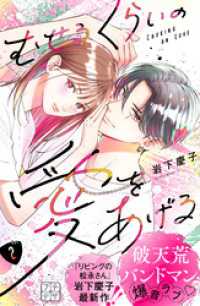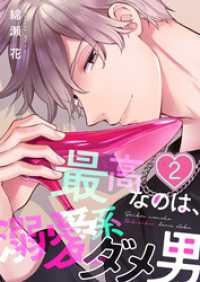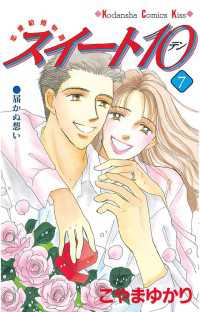出版社内容情報
街道が歴史を生み、
歴史が街道をつくってきた。
人々の営みの陰で栄えた土地、廃れた町。
ようこそ、歴史が織りなす街道の旅へ。
道は人生に喩えられることも多いが、日本史を紐解いていくと、道、つまり街道を舞台に歴史が生まれる場面に幾度となく遭遇する。だが、街道が歴史を生むだけではなく、歴史が街道を作ることも少なくない。
例えば、五街道の代表格である東海道は江戸と京都を結ぶ街道という印象が強いが、それは江戸に幕府が開かれてからのイメージに過ぎない。それまで、東海道は幕府が置かれた鎌倉と京都を結ぶ街道としての印象が強かった。しかし、徳川家康が江戸に幕府を置くことで、東海道は江戸と京都を結ぶ街道に変身する。また、我々がイメージする東海道の難所と言えば箱根峠だが、実は箱根峠を越えるルートは、もともとは東海道の本道ではなかった。本道は、足柄峠を越えるルートである足柄路だったのだ。江戸市中にも大量の火山灰が降ったという宝永の富士山の大噴火が本道を箱根路に変更させたことで、地域が変貌していく。
本書は、定評ある歴史研究者が、全国の街道と我々になじみの深い歴史とを重ね合わせ、様々なエピソードと新たな発見とともに綴る書き下ろし歴史ノンフィクション。五街道はもとより、熊野古道、伊勢参道、四国お遍路の道など、日本の歴史文化遺産ともいえる様々な道に秘められた歴史を明らかにしていく。
内容説明
「東海道より人気があった中山道」「一度、廃れた熊野古道」「4つあった日光街道」「将軍の緊急事態を想定していた甲州街道」―日本史を紐解いていくと、道、つまり街道を舞台に歴史が生まれる場面に幾度となく遭遇する。定評ある歴史研究者が、全国の特徴的な街道を取り上げ、様々なエピソードと新たな発見とともに綴る歴史読み物。
目次
松尾芭蕉は奥州街道で見た名所旧跡に何を思ったのか
日光街道は四つあった
鎌倉街道は常に「いざ鎌倉」への道だった
富士山の噴火で東海道のルートは変更された
参勤交代では東海道よりも人気があった中山道
甲州街道最大の宿場 内藤新宿はなぜ復活したのか
なぜ上杉謙信は北国街道を整備したのか
街道輸送の主力だった馬が街道名になった中馬街道
京都への道(京の七口)は明治維新の狼煙が上がった道でもあった
伊勢参宮街道からやってきたお伊勢参りはどんなもてなしを受けたのか
上皇や貴族は熊野古道をどのように旅したのか
なぜ西国街道は五街道にまさるとも劣らず賑わったのか
お遍路道はどのようにして生まれたのか
オランダ商館長一行は長崎街道で何を見たのか
武士の旅日記に国内の主要街道はどう書かれていたのか
著者等紹介
安藤優一郎[アンドウユウイチロウ]
歴史研究者(日本近世政治史・経済史専攻)。1965年千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業、同大学院文学研究科博士後期課程満期退学。文学博士(早稲田大学)。JR東日本「大人の休日」倶楽部のナビゲーターとして旅好きの中高年の人気を集め、NHKラジオ深夜便などでも活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
きみたけ
Book & Travel
ベローチェのひととき
Kaz