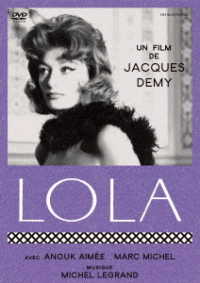出版社内容情報
私たちが目にする日本の農地には、とりわけ方形(正方形や長方形などの四角形)のものが多い。市街地でも、多くの街路が碁盤目のように直角に交差しているのが普通だ。一つひとつの宅地や施設の敷地もまた、方形の土地区画である。狭小な国土をくまなく区画するのであれば、蜂の巣状や三角形など、ほかの形状もあり得るし、世界を見渡せば、さまざまな形状の土地区画が見られる。本書の目的は、日本はなぜ、このような碁盤目の区画を志向するのかを探ることである。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
34
世界には様々なタイプの土地区画がある中、日本の碁盤目志向は際立つのはなぜか。条里制や地形条件、新田開発、圃場整備などの要因から考察する一冊。日本における弥生・古墳時代の水田跡や古代都市の方格プラン、条里制度や荘園、近世干拓新田、近世・近現代に作られた都市などのケース、また古代中国、古代ローマ、中世ヨーロッパ、米国やオーストラリアの都市などを事例として挙げて、どうしてそのようになっていったのかを考察する内容で、肝心のなぜ多いのかという部分は明確な答えがなかった気もしましたが、これはこれで興味深い考察でした。2023/02/19
chang_ume
10
耕地の土地区画に関する検討が多く、日本の条里プランと北米タウンシップが主な内容。ちなみに書題の「なぜ」に関しては本文ではほぼ言及されず。日本で碁盤目区画が多い理由として、条里プラン由来の景観意識形成をあとがきでちょろっと語りますが、正直肩透かしは否めない。また日本で碁盤目といえば城下町ですが、こちらもほぼ言及なし。中世にむしろ拡大した条里プラン、英国発・北米進展のタウンシップ、これら著者の新旧研究課題のダイジェストという中身だった。他著作の傾向を含めて、根源的な議論を先生はあまり好まないのかなと思った。2023/02/03
Teo
4
そりゃ班田収授の頃からやってるからなんじゃ?と思いつつまた別の理由もありかなと思ったが、そう違ってもいなかった。北海道の明治以降の原野を開拓した所はアメリカの影響もあってさもありなんだと思う。旧世界における土地計画はアメリカがどうしてそうなったかを除いたらあまり本書のタイトルとは関係ない様に見えた。2023/04/07
siomin
0
日経プレミアシリーズでもこのような切り口があるのかと感心しましたが、内容からしたら、碁盤目のほうが便利、に尽きるのかなと思います。城下町は敵の侵入を防ぐために曲がりくねった道にしておりそれが残っているところもありますが、けっこう碁盤目の城下町もあるんだなと。ヨーロッパやアメリカの例も豊富で、アメリカは確かに広大な土地には碁盤目のほうが良いだろうなと納得します。2025/01/25
まちこ
0
幻冬舎新書みたいななぜ系タイトルだから箸休め本かなと思って手にとったら著者が金田章裕でぜんぜんインスタントじゃなかった。この方の「地形と日本人」が超面白かったが今回はもうちょっと地味な内容。ヨーロッパの都市の無秩序に見える区画と日本の碁盤目区画は何が違うのか、ざっくり言うとそういう話で、結論もざっくり言うと中国文化の伝来・稲作志向・土地の狭さがあるらしい。世界様々な場所の区画には驚く。道から間口を狭く背後の開墾地をどこまでも広くとったドイツの例は日本でも畑作の開墾地に見られ、合理的理由がちゃんと存在する。2023/05/28