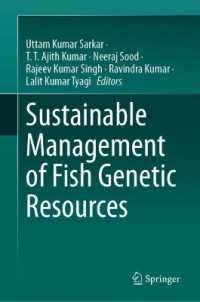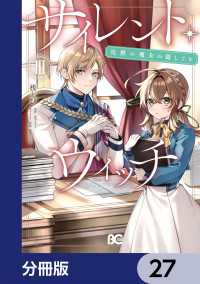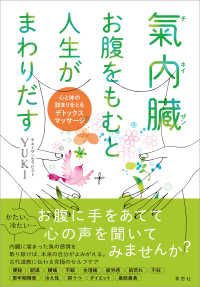出版社内容情報
インテル、アップル、グーグル、フェイスブック、アリババ……。世界を変えた企業の誕生と成長を演出したベンチャーキャピタルの内実を活き活き描く、興奮のノンフィクション。
・数多のスタートアップから原石を見つけ、世界を変革する巨大企業へと導くベンチャーキャピタル。彼らは、何に突き動かされ、どうやって企業(創業者)を見極め、どう育てて、莫大な投資収益を生み出していくのか――。
・下巻は「若者たちの反乱」=ベンチャーキャピタルの言いなりにならない創業者が登場、その代表格がフェイスブックのマーク・ザッカーバーグ、ショーン・パーカーだ。彼らがいかに衝撃を与えたか、そして新しい投資のかたちは、どのように生まれ発展したのかを描く。
・アリババをはじめ物語は中国も舞台とする。21世紀の初頭、巨大な経済マーケットを誇る一方、規制の厳しい大国に、どうやってマネーは入り込んでいったのかも、緻密な取材で明らかにする。
・ベンチャーキャピタルの誕生と進化・発展の物語ののちに、経済社会的な意義、また問題点などにも言及、著者の鋭い洞察力が光る論考も大いに参考になる。
内容説明
果敢な投資で絶大な富と力を手にしたベンチャーキャピタル。だが21世紀に入り、その権威と資金に目もくれぬ若者たちが現れる。その1人がフェイスブックを生んだマーク・ザッカーバーグだった。ピーター・ティールやアンドリーセンとホロウィッツなど、新たな世代が台頭し、投資家の世界にも変化の季節が訪れる。さらにマネーは海を越え、発展著しい中国で巨大ビジネスを生み出すが…。「べき乗則」が支配する世界の光と影を描く物語は、衝撃の展開へ。そして、ベンチャーキャピタルの本質と意義について鋭く分析、米中対立が厳しい現在における地政学的な意味も論ずる。
目次
第9章 ピーター・ティール、Yコンビネーター、そしてシリコンバレーの若者たちの反乱
第10章 中国へ、そしてかき回せ
第11章 アクセル、フェイスブック、そして凋落するクライナー・パーキンス
第12章 ロシア系、ヘッジファンド系、そして担い手が広がるグロース投資
第13章 全員で戦うセコイア
第14章 ユニコーンをめぐるポーカー・ゲーム
結論 幸運、スキル、そして国家間の競争
著者等紹介
マラビー,セバスチャン[マラビー,セバスチャン] [Mallaby,Sebastian]
米外交問題評議会で国際経済担当のポール・A・ボルカー・シニア・フェロー。主な著作にフィナンシャル・タイムズ紙とマッキンゼーが共同選考で2016年の最優秀ビジネス書に選んだThe Man Who Knew:The Life and Times of Alan Greenspan(邦訳『グリーンスパン:何でも知っている男』日本経済新聞出版)、More Money Than God:Hedge Funds and the Making of a New Elite(邦訳「ヘッジファンド:投資家たちの野望と興亡I、II』楽工社)など。オックスフォード大学で近現代史を学び、1986年の卒業後、エコノミスト誌に入り、南アフリカ、日本の駐在を経て1997-99年にワシントン支局長。1999年にワシントン・ポスト紙に移籍し、現在は客員コラムニスト。夫人はエコノミスト誌編集長のザニー・ミントン・ベドーズ氏
村井浩紀[ムライコウキ]
1984年に日本経済新聞社入社。ヒューストン、ニューヨーク、ロンドンに駐在。経済解説部長などを経て2018年から日本経済研究センター・エグゼクティブ・フェロー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
速読おやじ
しゅん
人生ゴルディアス
Hiroo Shimoda
takao