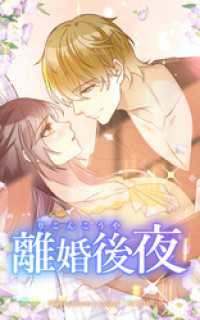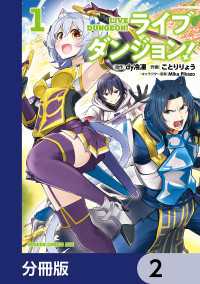出版社内容情報
EV先進国の欧州で見た、周回遅れの日本に突き付けられた現実。日米欧そして中国の各プレイヤーが繰り広げる熾烈な競争を活写する。
内容説明
このスピードに、日本は追いつけるか?EV先進地の欧州で見た、日本に突き付けられた現実。日米欧そして中国の各プレーヤーが繰り広げる熾烈な競争を活写する。
目次
序章 EV化する世界
第1章 EVガラパゴス日本の夜明け
第2章 最先端ノルウェーの現実
第3章 テスラを追え―第4章 電池の熱狂
第5章 死角を探る
第6章 中国の覚醒
第7章 国家の覇権争い
終章 自動車産業への提言
著者等紹介
深尾幸生[フカオコウセイ]
元・日本経済新聞フランクフルト支局長。現・日本経済新聞東京本社ビジネス報道ユニット記者。1982年生まれ。京都大学法学部卒業、ユトレヒト大学(オランダ)留学。2006年に日本経済新聞社に入社。自動車、電機、IT、鉄鋼などの各業界を担当。2009~13年テレビ東京に出向、経済ニュース番組などの制作に携わる。17年4月から22年3月まで、日本経済新聞フランクフルト支局で欧州企業を担当。なかでも電気自動車や再生可能エネルギーなど脱炭素に向けた動きを大企業からスタートアップまで幅広く取材(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mazda
38
バッテリ1つとっても、数の論理で多数が使い始めると安くなり、インフラ整備も整うことで、爆発的にユーザが増えるでしょう。ノルウェーは8割以上の車がEVですが、多大なコストをかけてまでEV化しており、世界も長期的にはEV化の波に乗らざるを得ないものと思われます。動く家電のようなものなので、テスラのようにこれまで車と関係ないメーカが参入しやすく、製品を差別化するのはユーザにとって魅力的なソフトウェアを作れるかどうかだろうと思います。これまでEVには否定的でしたが、好むと好まざるとEVシフトするしかないかな…。2023/09/26
kubottar
21
日本は自動車産業で飯を食ってるといっても過言ではないので、EV化に対して消極的であることは否めない。しかし、20年後のことを考えると早め早めに手を打っておかないと、取り返しがつかないかもしれない。この考え方というか、EVとガソリン車(ハイブリッド者)に対する海外との温度差が一番の問題だと感じました。2022/08/27
鶏豚
15
業務上、頻繁に話題にあがるEVの入門書。この手の著書は、学者や自動車評論家による偏った論調のものが多いが、本作は日経記者が西欧に長く滞在した経験をベースに、ニュートラルな立ち位置から今と未来を平易に語る良書。新車販売の6割強をEVが占めるノルウェーの背景。自動車産業の覇権争いとして先陣を切る英仏、譲らない独VW、ベンツ。追従出来ない欧州他国。勃興する中国メーカー。EV価格の4割を占めるバッテリー分野の熾烈な競争。面白かった反面、日本メーカーの存在感の希薄さに、未来の危機が垣間見える。(4.0/5点中)2023/01/06
おのちん
13
★★★★☆:非常に多くの事項がアップデートできた一冊だった。日本がモタモタしている間にEVだけでなく、電池やインフラ、リサイクルまで着実にピースをうめていく海外勢。また「EVの不都合な真実」の誤解との話。非常に興味深いものであった。2022/11/28
TAKA0726
9
21年のメーカー別EV販売台数は1位米テスラ、2位中国の上海汽車集団、3位独のフォルクスワーゲン、日産が仏ルノーとの連合の5位もホンダ27位、トヨタ29位。EVにすると電力が不足する、原発や火力発電を10〜20基作らなければいけない、はミスリード。これは国内すべての自動車6千万台を全部EVに置き換える試算。課題は充電インフラの整備や充電網の量より質、さらに高い価格で大衆車や小型車は厳しい。EVシフトにすると雇用の悪影響も懸念されるがシフトが遅れるほど雇用の影響が大きい見方もある。VWは民衆の車と言う意味。2022/12/27