出版社内容情報
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「めちゃ面白い!読むべし!」
―――慶応義塾大学環境情報学部教授、ヤフーCSO 安宅和人氏 推薦!
「この本で、日本は夢を取り戻せる」
―――オリエンタルラジオ 中田敦彦氏 絶賛!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
新興国に眠る課題、湧き起こる情熱
日本企業に生まれる新たな活躍の舞台
世界中の課題を見つける旅に出よう!
この30年、日本企業はグローバルでの存在感を徐々に失っていきました。
「GAFA」に代表される米国企業、「BAT」に代表される中国企業。
後塵を拝している日本企業ですが、今、新たに活躍の場が生まれています。
それが、「DeepTech(ディープテック)」です。
東南アジアをはじめとする新興国は、成長の過程で生まれる多くの課題を抱えています。そして、その課題から目を背けることなく、対峙する起業家たちが次々と生まれています。先端技術だけでなく、枯れた技術も応用しながら、直面する課題に対し、中長期的な視点に立って解決を目指していく。Deep Issue(ディープイシュー)をテクノロジーで解決していこうという取り組みを「ディープテック」と呼びます。
日本は戦後、製造業を中心に技術を磨き、世界でも有数の経済大国へと成長しました。磨いてきた多くの技術はテクノロジーの進化の過程で、過去のものになりつつあります。しかし、それらの「枯れた技術」が、もし新興国の課題解決につながるとしたら?新たな市場創造につながるとしたら?
ディープテックの領域では、必然的に投資期間は長くなるものの、解決したときの社会的インパクトはとてつもなく大きいものになります。しかも、日本企業が本来、得意としてきたすべてが活きてくる世界でもあります。
本書は、世界中のディープテックのケーススタディを多数収録しています。また、日本企業のビジネス開発部門、技術部門の方々にとって、有用となるフレームワークを紹介しています。大学生や研究者、起業を目指す人たちなど、幅広い方に読んでほしい1冊です。
日本のディープテックの始祖ともいえるリバネス代表取締役グループCEOの丸幸弘氏、『ITビジネスの原理』や『アフターデジタル』などのベストセラー本を通じて日本が進むべき道を照らし続けるフューチャリストの尾原和啓氏が、ディープテックの世界を描きます。
内容説明
国内外のディープテック事例を多数収録。新興国に眠る課題と湧き起こる情熱。日本企業に生まれる新たな活躍の舞台。
目次
1 ディープテックとは何か?(日本企業は「眠れる技術」の価値に気づけるか;非中央集権型社会に商機 ほか)
2 ディープテックの系譜を知ろう(日本は知識製造拠点として好立地;各エリアの時間軸を捉える「4D思考」 ほか)
3 海外で沸き起こるディープテック旋風(エアロダインが地域にもたらすもの;課題の当事者だからこそ生まれた「ReadRing」 ほか)
4 日本の潜在力はディープテックで開花する(チャレナジーは、「電力」と「つながり」を提供;バイプロダクト×ディセントラライズドのスタートアップ ほか)
著者等紹介
丸幸弘[マルユキヒロ]
2002年、東京大学大学院在学中に理工系大学生・大学院生のみでリバネスを設立。日本初「最先端科学の出前実験教室」をビジネス化した。大学や地域に眠る知識を組み合わせて新たな知識を生み出す「知識製造業」を営む
尾原和啓[オバラカズヒロ]
フューチャリスト。京都大学大学院で人工知能を研究。マッキンゼー・アンド・カンパニーやNTTドコモ、グーグル、リクルート、楽天など数多くの企業で新規事業立ち上げを担う。現在はシンガポール、インドネシアのバリ島が拠点(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
えちぜんや よーた
Willie the Wildcat
hit4papa
ミライ
-
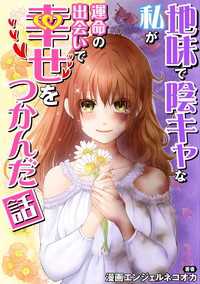
- 電子書籍
- 地味で陰キャな私が運命の出会いで幸せを…
-
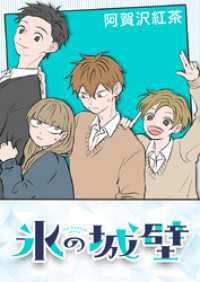
- 電子書籍
- 氷の城壁【タテヨミ】 81 マーガレッ…
-

- 電子書籍
- 陽気なクラウン・オフィス・ロウ 講談社…
-

- 電子書籍
- Mac Fan - 2015年10月号
-

- 電子書籍
- 超人ロック 完全版 (24)シャトレーズ




