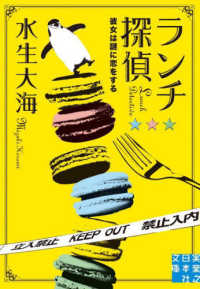内容説明
深い記憶の霧の中に、霞みゆく馬たちの島。住人ゼロ、上陸禁止、馬だけが暮らす現代のロスト・ワールド。木村伊兵衛賞写真家による“ユルリ島をめぐる冒険”の記録。
目次
プロローグ 幻の島への未完の航海日誌
失われた時を求めて(ユルリ島をめぐる6つの対話;鉄索のある崖の上で―最後の島民・庄林泰三;追憶の島は霧の向こうに―最初の馬生・庄林ヨネ;海風の中の楽園に生きて―根室の牧場主・佐々木徳太郎;伯楽は光と影を胸に刻む―別海の牧場主・大河原昭雄 ほか)
ユルリについて私が知っているいくつかの事柄(根室、国後、そしてユルリへ;国後にまつわるスクラップ;道東の馬に息づく気高い血脈;理想郷を支えた名牧場の記憶;花園効果と白い花弁の不思議 ほか)
エピローグ 幻の島
著者等紹介
岡田敦[オカダアツシ]
写真家・芸術学博士。1979年、北海道生まれ。2003年、大阪芸術大学芸術学部写真学科卒。2008年、東京工芸大学大学院芸術学研究科博士後期課程にて博士号を取得。同年、“写真界の芥川賞”とも称される木村伊兵衛写真賞を受賞。その他、北海道文化奨励賞、東川賞特別作家賞、富士フォトサロン新人賞などを受賞。作品は北海道立近代美術館、川崎市市民ミュージアム、東川町文化ギャラリーなどにパブリックコレクションされている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しげ
57
根室市昆布盛の沖合いに在る無人島「ユルリ島」仕事の都合で数年おきに道東を訪れる機会が有りましたが海岸沿の国道を通過する程度で、存在と経緯を知ったのは近隣(浜中町)で動物王国を運営していた故、畑正憲さんのテレビ番組だったと思います。道内の炭鉱、漁港は時代の隆盛衰退で置き去りとなった地域も多い。荷役を終え島に残された馬の営みは人の都合とは別に逞しさと美しさを感じます。2025/02/19
いちろく
29
紹介していただいた本。北海道にあるユルリ島、かって昆布漁の労力の為に移入された馬が、無人島になった今も野生化して生きている場所である。写真家である著者が、ユルリ島の人と馬に関する記録が無いと知り、現地の写真と当時の昆布漁に関わった人達へのインタビューを基にまとめたのが本書。馬にとっては環境的にも理想郷である一方、繁殖や維持の兼ね合いから何れは無くなる運命である点には寂寥感も覚えた。上下二段組の分量が気にならないほど夢中で読み終えていただけでなく、適宜挿入される馬を主としたユルリ島の風景がとにかく美しい。2024/12/22
Toshi
24
河崎秋子「颶風の王」のモデルになった孤島の馬たちの写真ルポ。根室市の沖にあるユルリ島に大正時代から昆布漁の労働力として放牧されていた馬は、戦後島が天然記念物となり、また昆布漁の変遷により島に置き去りにされる。島には草や水も豊富で馬たちは野生化し繁栄するが、近親交配による繁殖を避けるため雄馬だけが島から連れ出され、雌馬だけとなった馬たちは消えゆく運命となる(2017年で残された馬は3頭)。馬たちにとってなにが最善なのか?そんな人間たちの安易な心配をよそに、馬たちは「颶風の王」で描かれたままに神々しく美しい。2025/07/04
OHモリ
23
ユルリ島はエトピリカの国内最後の繁殖地で、希少鳥類に指定されているチシマウガラスも繁殖していて自然保護のため立ち入り禁止になっている。日本最東端根室沖にあるその無人島に許可を得て通い詰めた写真家岡田敦さんが書いたのがこの本。インタビュー記事とエッセイのある写真集というよりも記録集だろうか。写真は写実的でかつ哀愁を感じさせられる。2023年度JRA賞馬事文化賞受賞作。詳細はblog→https://plaza.rakuten.co.jp/drunk4374books/diary/202411170000/ 2024/10/03
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
21
積読チャンネルで紹介されていたので手に取る。立ち入り禁止の無人島で、ただ滅びることを待つだけの馬たち。対岸から見つめるしかできない人たち。島に馬が連れてこられたのは北の海での昆布漁のためだった。馬とは産業動物、馬の力を借りる必要のなくなった現代では馬牧場というものも存在を許されなくなる。滅びいくのは馬だけではなかった。人間以外の生き物が生きていけない世界とは、いずれ人間の首も絞めることになるのだろう。2025/02/17