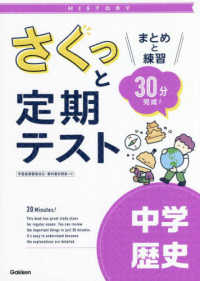感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Akihiro Nishio
25
先日栃木出張の際に寄った足尾銅山を復習する。江戸時代には山師が露出した鉱脈を発見したのち、手堀りで鉱脈を掘り進め、それが尽きたら放棄するという方法であったこと、明治以降の鉱山大躍進の時代に燃料として森林が刈り出された為洪水が頻発、栃木南部の遊水池はそのために設けられたことなどを知る。しかし、鉱毒が化学的に何であったのか、どう処理すれば良かったのかという理系的な問いには答えず。また、意外にも半分以上は足尾地区を散策しながら、郷土史を引きながら当時の様子を振り返るという構成。観光案内だったのかな?2018/07/30
いわちき
1
1610年に露頭が発見されて以来、1973年まで銅にまつわる人の営みの歴史を紡いできた足尾銅山。その負の歴史は大きいが東洋一の銅山として日本の近代化に大きく貢献した山である。電気機関、坑内のベルトコンベヤーの話などは、先日読んだ美術手帖の中の後美術論 (椹木野衣)の畠山直哉、陸前高田、秩父盆地のコンクリートという異形の形になり都市に身を刻み込んだ石灰石鉱山話。岩崎貴宏(鷲田めるろ評)の山から都市へ繋がれる送電線の作品の話と接続する。2015/09/14
しょー
0
足尾銅山と言えば、小学校の社会科で学ぶ田中正造以外に何も知らなかったが、何気なく旅行に行って足尾銅山の光の部分を知る。この本でそのリアリティを感じるのは難しいが、今の現地の写真をいくら掲載しても伝えるのが難しい場所という事は現地に行った人にはわかると思う。この本を何かの機会に手に取って、現地に行ってみたいという人が少しでも出てくればいいなと思う。2019/07/07