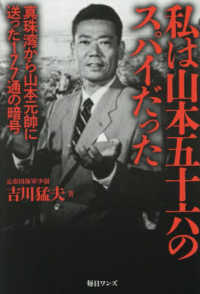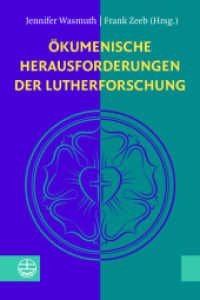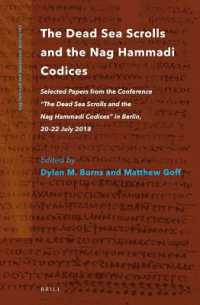出版社内容情報
バッハから現代まで、時代を代表する作曲家を取り上げ、彼らにまつわる通説を検証する。意外な実像が浮かびあがり、通説が生まれた背景をさぐる、目からウロコの音楽史。
内容説明
ベートーヴェンを「楽聖」に仕立てあげたのは誰?ロッシーニが37歳で引退した真の理由は?シューベルトはじつはお金持ちだった?―エピソードでつづる、目からウロコの音楽史。
目次
歴史の闇から蘇ったバッハの物語
作曲家たちのバッハ体験
モーツァルトはいつから「神の子」となったのか
楽聖に託された近代の理想―ベートーヴェンはなぜ逸話だらけなのか
ロッシーニはなぜオペラ創作の筆を折ったのか
清く貧しい薄幸の音楽家シューベルト―『未完成交響楽』のイメージは真実か?
ベルリオーズは誇大妄想症?
ブラームスは近代の夕暮れの響き
批評家の見たリヒャルト・ヴァーグナー
『モルダウ』の裏に流れる民族の想い―スメタナの抱いた理想と現実
プッチーニははたして様式の乗っ取り屋か?
ロシア国民楽派の作曲家はアマチュア?
近代フランス音楽の生みの親、サン=サーンスはなぜ嫌われるのか?
著者等紹介
西原稔[ニシハラミノル]
山形県生まれ。東京芸術大学大学院博士課程満期退学。桐朋学園大学音楽学部教授・学部長。18、19世紀を主対象に音楽社会史や音楽思想史を専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
1959のコールマン
63
☆4.5。タイトルから、ゴシップかバクロものかと勘違いしそうだが、案外まとも。音楽資料を丁寧に読みときながら書いた本と言える。内容は、やはり大家が本文の大部分をしめる。特にバッハが詳しい。ただバッハ本人というより、バッハ死後の事が中心。楽譜を巡るいざこざや、バッハがどのように世の中に受け入れられていったかを詳しく書かれている。いやあ、19世紀になっても多くの聴衆にとってバッハは「混乱した音のかたまり」p32「私に金と時間を返せ」p37だったのね。その他、ロッシーニがオペラ創作をやめた理由が「政治」。↓2021/03/31
ジャッキー
0
シューベルトは実は貧乏じゃなかったとか、ベートーヴェンの言ったとされる言葉は実は秘書が会話帳に書き足していたとか、裏話的な話が多く、面白かった。2015/02/21
かーむ
0
図書館。だいたいの歴史の流れがわかるし、書簡や批評文なども多かったので面白かったです。2014/09/28
左近
0
バッハの死後に起きた楽譜争奪戦や、ベートーヴェンの筆談記録を改竄した押しかけ秘書など、著名な人物と、その周辺に光を当て、一般的なイメージの信憑性について考えてみるなど、“裏読みクラシック史”といった感じ。ニュー・イヤー・コンサートでお馴染みの『ラディツキー行進曲』は、イタリア独立運動を鎮圧した将軍を称えた作品だったとは!気軽に手拍子をしながら楽しめる曲じゃなかったようだ…ロシアの血は入ってないけどロシアの作曲家に分類されるセザール・キュイは、築城学の権威でもあったとのこと。どんな城を造ったのか、気になる。2014/01/20
ゆんぽん
0
章末のコラム(〇〇の周辺の音楽家たち)は要らない。ただでさえ各章の中心人物の力の入れ方がわかる(バッハ・モーツァルト×)のに更に登場人物を増やし混乱させてくれた… ベートーベンとロッシーニの章はわかりやすい。得にロッシーニと政治の関係は初めて聞いたので《老年のいたずら》を観て晩年の彼を推察したい。東北で上演しないかな。全部を読もうとせず、気になる音楽家をチョイスした方が◎2010/11/17
-
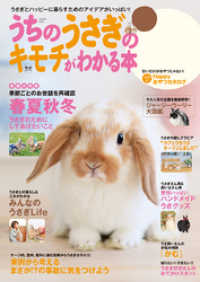
- 電子書籍
- うちのうさぎのキモチがわかる本 春&夏…