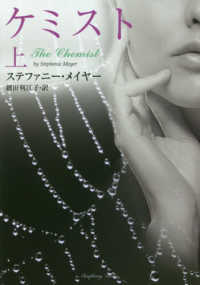出版社内容情報
「教材づくり(何を教えるか)」に主眼を置くのではなく、「この授業をどう進めるか」という指導法を中心に据えた音楽指導の手引。
音楽科の表現領域の1分野「音楽づくり」には、実りある音楽教育を実現する可能性を秘めているが、その指導内容や指導法にはまだまだ開発の余地が多い。本書は「教材づくり(何を教えるか)」に主眼を置くのではなく、「この授業をどう進めるか」という指導法を中心に据えたのが特徴。卓越した授業を臨場感あふれるレポート形式で紹介し、音楽づくりの授業において教師がどう立ち回れば良いか、そのコツを抽出していく。著者は教育実践・研究校として知られる筑波大学附属小学校の若手教師で、この「音楽づくりの言葉がけ」において突出した実績を持つ。
まえがきにかえて
序章 私が音楽づくりで大切にしていること
第1章 音楽づくりの授業リポート
FILE 0 1人ずつ座るゲーム ゲームに宿る音楽づくりの萌芽
FILE 1 打楽器で1人1音 学習のルールと音を慈しむ心を学ぶ
FILE 2 手拍子の音楽づくり 絞られた「条件」が引き出すクリエイティビティ
FILE 3 1音アドリブ ごくシンプルなことからステップを踏んでいこう
FILE 4 音型の分析 「考えること」「議論すること」を楽しもう!
FILE 5 ?T-?W-?X-?Tの旋律づくり 知識を音楽づくりで身につける
(FILE 5 の続き)音楽を「完成」させていく子どもたちのドラマ
FILE 6 役割のある音楽 音楽づくりで「生き方」を学ぶ
第2章 音楽づくりの授業Q&A
Question 1 年間を通して行う みんなが安心して表現できる環境づくり
Question 2 授業時数を有益に使うための横断的な授業時間の使い方・年間計画
Question 3 音楽科の学びは「感じ取って、考える」 音を通して考えることも「言語活動」
Question 4 音楽づくりの授業は子どもたちと一緒につくり上げていくもの
Question 5 音楽づくりのモチベーションとは? 「思いや意図」とは?
Question 6 子どもたちが自ら考え、必要性を感じる授業のルールと伝え方
Question 7 共通事項・音楽用語は名前よりも本質を感じて学ぶ
Question 8 板書や記譜をする・させる時は目的や意義を忘れないで
Question 9 シンプルな条件設定のねらい 子どもの思考を揺さぶる条件の提示
Question 10 「まとまり・つながり・終わり」を音楽づくりの手がかりに
Question 11 器楽の演奏技能・楽器の特性も気に留めて
Question 12 グループ分けは活動への意欲と成果を大きく左右する
Question 13 「即興表現」「つくり上げる」「完成させる」それぞれの意味と価値
Question 14 子どもの表現や思考を中心にした授業をするための教師の視点
Question 15 教師の価値観の押しつけにしない 音楽づくりでのアドバイスの在り方
Question 16 グループ活動での個別指導・中間発表の目的、指導のポイント
Question 17 表現を「聴く力」と「まねに対する価値観」を育てる
Question 18 ピンチを成長のチャンスに変えるための言葉がけとサポート
Question 19 みんなが音楽を好きになれる 子どもの見方・個性の伸ばし方
あとがき
【著者紹介】
筑波大学附属小学校教諭。
目次
第1章 音楽づくりの授業リポート(1人ずつ座るゲーム―ゲームに宿る音楽づくりの萌芽;打楽器で1人1音―学習のルールと音を慈しむ心を学ぶ;手拍子の音楽づくり―絞られた「条件」が引き出すクリエイティビティ;1音アドリブ―ごくシンプルなことからステップを踏んでいこう;音型の分析―「考えること」「議論すること」を楽しもう! ほか)
第2章 音楽づくりの授業Q&A(年間を通して行うみんなが安心して表現できる環境づくり;授業時数を有益に使うための横断的な授業時間の使い方・年間計画;音楽科の学びは「感じ取って、考える」音を通して考えることも「言語活動」;音楽づくりの授業は子どもたちと一緒につくり上げていくもの;音楽づくりのモチベーションとは?「思いや意図」とは? ほか)
著者等紹介
平野次郎[ヒラノジロウ]
筑波大学附属小学校教諭(音楽科)。1981年福岡県生まれ、千葉県育ち。尚美学園大学(ジャズ&ポップス専攻)を卒業後、千葉県の公立中学校・小学校勤務を経て現職。研究テーマは「対話する音楽授業づくり―思考力とコミュニケーションに視点をあてて」。音楽づくりや即興表現、iPadを活用した授業構成、鍵盤ハーモニカやリコーダーの新たな活用方法を切り口に研究を進めている。全国各地の研究会や研修会等で、主に「音楽づくり」の指導法や授業アイデアの講師を務め、好評を博している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。