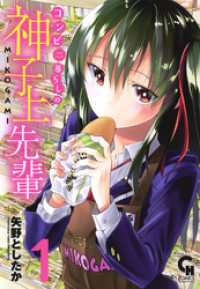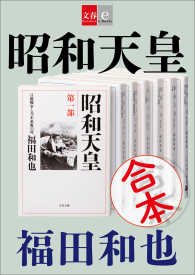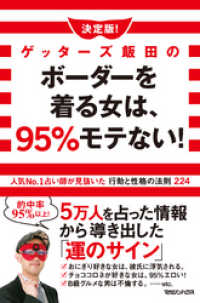- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 演劇
- > オペラ・ミュージカル
出版社内容情報
世界のオペラ上演の最高峰、ウィーン国立歌劇場を、ソフト、ハード両面から大解剖。日々の公演から、文化遺産としての劇場まで。
2002年に小澤征爾が音楽監督になったという大きな話題もあったが、もとよりウィーンはクラシック・ファン憧れの地。世界でも最高峰の人気・実力をほこるオペラの殿堂、ウィーン国立歌劇場のことを知りたい人は多い。オペラに造詣が深い人から、一回でもいいからウィーンでオペラを聴きたいという人にも、ウィーンの豊かな音楽状況と、本場のオペラとはどういうものかを紹介する。さらに、見えない運営部門にまで深く入りこめるのは筆者ならでは。巨大なハード「入れ物」だけでなく、舞台の裏には何倍もの人間が動いている巨大なソフトの集積であること、オペラ劇場は特別な存在、文化財産であること知ってもらいたいということから、人気の歌手の話から、たくさんのハード、ソフトのシステムを盛り込んだ。ウィーン国立歌劇場を知れば、オペラとはオペラ劇場とは何かが見えてくる。本場でオペラが観たい!ウィーンに行きたい!と思わせる本。
第1章:レパートリー・システム/第2章:煌めく歌手たち/第3章:奥行きを深める「脇役」たち/第4章:ウィーン国立歌劇場総裁/第5章:指揮者群像/第6章:ドラマトゥルグとは?/第7章:演出家と演出/第8章:ウィーン国立歌劇場管弦楽団とウィーン・フィル/第9章:ウィーン国立歌劇場バレエ団/第10章:ウィーン国立歌劇場合唱団/第11章:熟練の裏方たち/第12章:さかんな海外公演、重要な日本公演/第13章:一年で最も輝く日 オーパン・バル/第14章:特殊な建物、特別な聴衆/巻末:ウィーン国立歌劇場の公演を収録したCD・DVD一覧、参考文献資料一覧
【著者紹介】
1933年鹿児島生まれ。早稲田大学大学院博士課程単位取得。ウィーン大学、ウィーン国立音楽大学に留学。鹿児島短期大学教授、東邦音楽大学教授・理事、九州大学客員教授など歴任。霧島国際音楽祭創設。第1回音楽之友社賞共同受賞。『ショパン全集』(パデレフスキ版・日本版)編集委員並びに訳。『ウェストミンスター復刻盤CDシリーズ』資料調査、執筆。『音楽の友』『ムジカノーヴァ』など多くの音楽雑誌、新聞に執筆。著書に『ウィーン・フィルハーモニー』(中央公論新社)、『ウィーン三昧』日本図書館協会選定図書(ショパン社)、『「音楽的」なピアノ演奏のヒント』(音楽之友社)、共同執筆に『小澤征爾とウィーン』(音楽之友社)、『ウィーン・フィルハーモニー&ベルリン・フィルハーモニー』(音楽之友社)、『新編ウィーンの本』(音楽之友社)、訳書にJ.N.ダーヴィド『二声インヴェンションの研究』(音楽之友社)など。現在ウィーン・メロス音楽研究所代表、早稲田大学エクステンションセンター講師。ウィーン在住。
内容説明
多くの歴史的困難を乗り越えて、ウィーン国立歌劇場がどのよう進んできたか。現代のスター歌手の話題から劇場の運営にまで深く入っていき、ウィーンの豊かな音楽状況とともに、オペラとは、オペラ劇場とは何か、まさにすみからすみまでを紹介する。本場でオペラが観たくなる本。
目次
レパートリー・システム
煌めく歌手たち
奥行きを深める「脇役」たち
ウィーン国立歌劇場の総裁
指揮者群像
ドラマトゥルグとは?
演出家と演出
ウィーン国立歌劇場管弦楽団とウィーン・フィル
ウィーン国立歌劇場バレエ団
ウィーン国立歌劇場合唱団
熟練の裏方たち
さかんな海外公演
一年で最も輝く日 オーパンバル(オペラ座舞踏会)
特殊な建物、特別な聴衆
著者等紹介
野村三郎[ノムラサブロウ]
1933年鹿児島生まれ。早稲田大学大学院博士課程単位取得。ウィーン大学、ウィーン国立音楽大学に留学。鹿児島短期大学教授、東邦音楽大学教授・理事、九州大学客員教授など歴任。霧島国際音楽祭創設。第1回音楽之友社賞共同受賞。現在ウィーンメロス音楽研究所代表、早稲田大学エクステンションセンター講師。ウィーン在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。