出版社内容情報
本書では、気鋭の音楽学者である著者が「私はなぜ音楽評論を書くのか」という自身への問いを根源として、歴史的事象を読み解きながら音楽評論そのものを客観的に探究する。本書の起点となる1875年(明治8年)『東京日日新聞』の記事から、今日に至るまで約150年。音楽文化は、音楽評論によって多様な人々が輪を作りその車輪を動かし続けてきた。本書は、新聞の音楽評論、音楽雑誌、芸大楽理科、音楽之友社、遠山一行、吉田秀和ほか、音楽評論にとって重要で興味深い9つのテーマを時系列的に扱い、極力、評論自体を紹介しながら展開。インターネット社会の今だからこそ、あらためて日本の近代150年のスパンで音楽評論とは何かを問う渾身の一冊。
内容説明
福地桜痴、四竈訥治、大田黒元雄、堀内敬三、河上徹太郎、吉田秀和、雑誌『音楽と文学』、『音楽之友』、芸大楽理科…。明治維新から150年余りの近現代史の中で音楽評論家とメディアはどう育まれたか?音楽評論そのものの意味を問い直す!
目次
第1章 「音楽がわからない」音楽評論家―福地桜痴と『東京日日新聞』
第2章 学校音楽に期待をかける『音楽雑誌』―四竈訥治の時代
第3章 「一私人の一私言」を超える演奏批評―一八九八年(明治三一年)の『読売新聞』から
第4章 楽壇の画期としての同人雑誌―『音楽と文学』とその周辺
第5章 音楽評論家の社会的認知と音楽著作権―昭和初期の批評のすがた
第6章 「近代の超克」と大東亜共栄圏―総力戦体制下の洋楽と音楽雑誌の統廃合
第7章 アカデミズムとジャーナリズム―東京帝国大学美学美術史学科から東京芸術大学楽理科開設へ
第8章 「健全な聴取者」というヒューマニズム―遠山一行の音楽評論
第9章 「音楽的自我」を生きる―吉田秀和の評論活動
著者等紹介
白石美雪[シライシミユキ]
音楽学者、音楽評論家。武蔵野美術大学教授。著作に『ジョン・ケージ混沌ではなくアナーキー』(武蔵野美術大学出版局、第20回吉田秀和賞受賞)など。NHKラジオにレギュラー出演し、朝日新聞で音楽会評、各種雑誌で音楽評論を執筆している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
みつ
takao
-

- 電子書籍
- UX原論 - ユーザビリティからUXへ




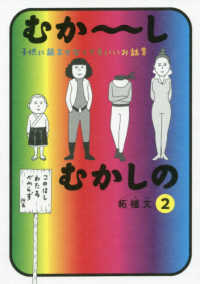
![Dementia [3 volumes]](../images/goods/ar/work/imgdata2/FC03133/FC0313384347.JPG)


