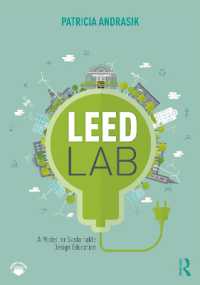目次
1 プロローグ―ドラマとしてのオペラ
2 オルフェウス―ギリシア劇の復興
3 暗黒時代
4 筋の展開と音楽の連続性
5 モーツァルト
6 ヴェルディの『オテロ』―伝統的オペラとシェイクスピアのオセロ像
7 歌う劇としてのオペラ
8 交響詩としてのオペラ
9 揺り戻し―『ヴォツェック』と『放蕩児の遍歴』
10 劇とその代用品
11 エピローグ―オペラの批評について
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kthyk
12
ロマン主義時代の「音楽と建築」の検討を進めている。テーマは「音楽の自律」と「オペラ」。この書は「オルフェオ」から「ヴォツェック」までのオペラを「ドラマ」の文化史として明快にまとめた名著。オペラブッファが持つ音楽の連続性が劇的音楽の道を開いた。器楽音楽の劇的連続性を生み出したのはソナタ形式を支えた調性。18世紀の器楽曲はこの形式の展開により葛藤・経過・興奮・変化という絶え間ない変化が可能となり、劇的連続性が生みだされる。しかし、20世紀、シェーンベルクは調性を捨て無調音楽、その意味と展開は「幻想曲風に」へ。2020/12/22
千葉さとし
0
教科書的に読んでいたので時間がかかりました。オペラ史を名作の検証によって辿り、その可能性と面白さについて考える本、こういうのが批評ですよね。もし全部読むのは…と思われた方、エピローグだけ先に読んで、著者の愛の重さを知れば楽しく読めるかもしれませんよ?(笑)2011/12/08