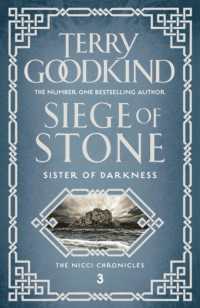内容説明
従来の音楽史本は概論・定説による教科書的なものが多かったが、本書は著者の長年の研究から導き出される豊富な知識、独自の視点・推論を軸として一歩も二歩も踏み出した内容で、未来への橋渡しとなる。著者の専門のキリスト教音楽については、ヨーロッパ音楽の基礎として音楽史の流れの中で、とくに充実してわかりやすく書かれている。古代、中世、ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派、ロマン派以後の歴史区分については、独自の考え方による区切り目を示し、時代の転換期の記述が興味深く展開する。
目次
第1章 古代の音楽
第2章 中世の音楽
第3章 ルネサンス音楽
第4章 バロック音楽
第5章 古典派
第6章 ロマン派
第7章 ロマン派以後
著者等紹介
金澤正剛[カナザワマサカタ]
1934年東京生まれ。1966年にハーヴァード大学博士課程(音楽学)を修了。その後、同大学ルネサンス研究所(フィレンツェ)の所員、複数の大学の非常勤講師、米国の大学の客員教授などを務め、1982年に国際基督教大学教授、兼同大学宗教音楽センター所長、2004年に名誉教授。現在日本リュート協会、日本イタリア古楽協会、日本ヘンデル協会などの会長。著書『モンテカシノ手稿譜第871号』(共著)で1980年度ASCAP賞を、『古楽のすすめ』で1998年日本ミュージック・ペン・クラブ大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
67
音楽史の本は、通常「中世・ルネサンス」から始まる。私はかねがね、哲学・数学・演劇・彫刻などが、ギリシャ・ローマ時代にあれほどの高みに到達したのに、音楽は近世まで一体何をしていたのかと訝しく思っていたが、この本は、きちんと古代から説き起こしてくれる。厳格なピュタゴラス音律によって三度の音程を不純な響きと見做していたものを、中世になって、ごく微量調節することによって響きのよい三度や六度を得られることを発見して、音楽芸術が一気に開花したと言う。目から鱗が落ちる解説だが、随所でそんな驚きに出会うとてもいい本だ。2020/09/30
おだまん
3
体系的だし、押さえるべきところは網羅していて分かりやすい!世界史ちゃんと勉強しておけばよかったなーと今更ながら思う。手元において線を引っ張りながら音源を聴いていきたい。2020/08/15