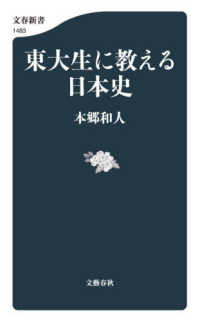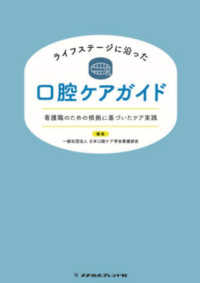出版社内容情報
パリ音楽院に学んだ3人の作曲家が、伝統的コラール技法の概論と実習をまとめた本邦初の書。作曲科受験生、学生、指導者必携。
パリ音楽院に学んだ3人の作曲家が、伝統的なコラール技法の概論と実習についてまとめた本邦初の書。作曲科受験生、学生、指導者必携。2014年(平成25年度)より東京芸術大学作曲科入試で出題されるコラール技法を学べる唯一のテキスト。
コラール技法はバッハの音楽における重要な作曲法であるのみならず、ルネサンス・バロック期の対位法から、通奏低音技法を介して古典派以降の和声法に移行する経緯を学ぶうえで必須という。
ソルフェージュ(視唱・聴音)、ピアノ初見視奏(スコアリーディング)、声楽・器楽アンサンブル、通奏低音法、音楽分析の教材としても最適。バッハからシェーンベルクにいたる音楽様式の理解にも必須。
課題は、パリ音楽院の作曲書法クラスに学んだ山口博史、林達也両氏の書き下ろし。パリ音楽院のコラール課題実施例も収録。概論と分析は、高音部記号と低音部記号による。実施篇・範例はハ音記号と低音部記号による4段譜。
第1部 コラール概論
1 バッハのコラールについて
2 通奏低音法について
3 バッハのコラール分析――《マタイ受難曲》より5曲のコラール
4 キルンベルガーによる、バッハ様式のコラール技法について
5 コラール技法の学習
第2部 実施篇
1 書法上の留意点
2 非和声音(和音外音、転位音)について
3 和声の諸規則
4 数字付き低音――12のバス課題付き
5 バッハのコラールの実例と分析――ブライトコプフ版《4声のコラール歌曲集》より10曲のコラール
第3部 コラール課題と範例(60題)
1 コラール課題
2 範例集
3 パリ国立高等音楽院のコラール課題実施例(範例)
【著者紹介】
東京藝術大学、パリ国立高等音楽院、ウィーン国立音楽大学で学ぶ。クセナキス作曲コンクール(パリ)第1位、国際現代音楽協会(ISCM)「世界音楽の日々」に入選。著書に『作曲の思想――音楽・知のメモリア』(アルテスパブリッシング)、『作曲の技法――バッハからウェーベルンまで』(音楽之友社)などがある。東京藝術大学作曲科教授、慶應義塾大学講師。
内容説明
パリ国立高等音楽院に学んだ3人の作曲家による日本初のコラール技法教程と範例集。
目次
第1部 コラール概論(バッハのコラールについて;通奏低音法について;バッハのコラールの分析―『マタイ受難曲』より5曲のコラール;キルンベルガーによる、バッハ様式のコラール技法について;コラール技法の学習の歴史的意味)
第2部 実施篇(書法上の留意点;非和声音について;和声の諸規則;数字付き低音―12のバス課題付き;バッハのコラールの実例と分析―ブライトコプフ版『371の4声コラール集』より10曲のコラール)
第3部 コラール課題と範例(コラール課題;範例;パリ国立高等音楽院のコラール課題実施例(範例))
著者等紹介
小鍛冶邦隆[コカジクニタカ]
東京藝術大学、パリ国立高等音楽院、ウィーン国立音楽大学で学ぶ。クセナキス作曲コンクール(パリ)第1位、国際現代音楽協会(ISCM)「世界音楽の日々」他に入選。東京藝術大学音楽学部作曲科教授、慶應義塾大学講師
林達也[ハヤシタツヤ]
作曲家・ピアニスト。東京藝術大学在学中に日仏現代音楽作曲コンクールで第1位、朝日作曲賞、神戸国際フルート作品作曲コンクールなどに入選。フランス政府給費留学生としてパリ国立高等音楽院で作曲、エクリチュール(和声、対位法、フーガ)、声楽伴奏、ピアノ伴奏法、管弦楽法、クラヴサン、通奏低音の各科で学び、1等賞を得て卒業。パリ・エコールノルマル音楽院ピアノ科最高課程を首席で卒業。マルメゾン市立音楽院でヴィルトゥオーゾ賞。帰国後、ソロ・リサイタルをはじめ声楽・器楽の室内楽や現代音楽の初演など幅広く活動。日本ソルフェージュ研究協議会前理事。「翼の会」音楽監督。東京藝術大学音楽学部ソルフェージュ科准教授を経て、同大学同学部作曲家准教授
山口博史[ヤマグチヒロシ]
立教大学卒業。1971年より島岡譲氏に和声、フーガを師事。1973‐80年パリ国立高等音楽院に留学。1975年和声首席1等賞、1976年対位法首席1等賞(ノエル・ギャロン賞)、1977年フーガ1等賞。シャラン、アンリ、ビッチ、カステレード、コンスタンの各氏に師事。1980年より国立音楽大学音楽学部作曲家で教鞭をとる。現在同大教授。1981年より東京藝術大学音楽学部ソルフェージュ科講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。