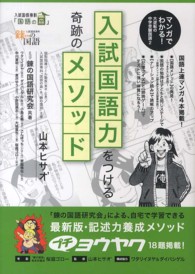出版社内容情報
線から出発し和音に至るパレストリーナ様式対位法の教科書。対位法理論の歴史的概観、パレストリーナ様式の技法上の特徴、実習。
和声を内包した線的な音楽であるバッハの様式に対し、純粋に線と線の関係を追求するパレストリーナの様式について書かれた名著中の名著、ついに復刊! 原書は、1931年の初版以来、高い評価を得ている。その日本語訳である本書は、東京創元社より1955年に刊行されたのち絶版となり、長らく復刊が待たれていたもの。
全体は、対位法理論の歴史的概観、パレストリーナの技法上の諸特長、実習の順で構成され、カノン、モテット、フーガにもふれている。
明晰な説明、豊富な譜例に加え、理論と実践の問題が絶妙のバランスで扱われている点で、実習書としてばかりでなく、音楽学の演習書としても利用可能。本書を通じて、16世紀の声楽ポリフォニー様式の「実態」をぜひ学んでほしい。
翻訳では、読譜の便などに配慮し、すべての譜例を高音部記号と低音部記号に統一している。この譜例の書き直しを小澤征爾氏が、索引作成を中野博司氏がそれぞれ担当した。
本書の編集について
序言
第1部 序章
第1章 対位法理論の歴史的概観
§1 対位法とその対照としての和声法
§2 9世紀から14世紀まで:対位法理論の創始期
§3 15世紀:諸原理の成立
§4 16世紀:パレストリーナ様式
§5 17世紀:教授上の体系の発達
§6 18世紀:バッハ様式
§7 19世紀:パレストリーナかバッハか?
§8 フックス以後の「パレストリーナ運動」
第2章 技法上の諸特長
§1 記譜法
§2 教会調
§3 旋法
§4 和声
第2部 対位法実習
序論
第3章 2声対位法
§1 第1種
§2 第2種
§3 第3種
§4 第4種
§5 第5種
§6 2声の自由対位法
§7 模倣
第4章 3声対位法
§1 第1種
§2 第2種
§3 第3種
§4 第4種
§5 第5種
§6 模倣
第5章 4声対位法
§1 第1種
§2 第2種
§3 第3種
§4 第4種
§5 第5種
§6 模倣
第6章 4声以上の対位法
第7章 カノン
第8章 モテット
第9章 ミサ
補遺
声楽フーガ
2重・3重・4重対位法
最も主要な規則の総括
§1 旋律
§2 協和音の連結
§3 不協和音の連結
訳者あとがき
索引
【著者紹介】
著:デンマークの音楽学者、作曲家(1892-1974)。日本では、クヌズ・イェペセン、クヌズ・イェバサンとも表記される。1949-52年まで国際音楽学会会長。パレストリーナ研究の第一人者として、イタリア・ルネサンス音楽の解釈に決定的な影響を与えた。同郷のカール・ニルセンと深い親交を結び、作曲家としても活躍。とりわけ声楽曲に優れたものが多い。
内容説明
16世紀声楽ポリフォニーの最良の教科書、ついに復刊!和声を内包した線的な音楽であるバッハの様式に対し、純粋に線と線の関係を追求するパレストリーナ様式の対位法を、豊富な譜例とともに、明晰に解説。理論的問題と実践的問題が絶妙のバランスで扱われ、音楽技法の基本原理を正確に学ぶことができる。
目次
第1部 序章(対位法理論の歴史的概観;技法上の諸特徴)
第2部 対位法実習(2声対位法;3声対位法;4声対位法;4声以上の対位法;カノン;モテット;ミサ)
補遺(声楽フーガ;2重・3重・4重対位法;最も主要な規則の総括)
著者等紹介
柴田南雄[シバタミナオ]
作曲家(1916‐1996)。1939年東京帝国大学理学部植物学科・1943年同大文学部美術史学科卒業。作品:『追分節考』(1973年)など
皆川達夫[ミナガワタツオ]
音楽学者(1927‐)。1951年東京大学文学部西洋史学科卒業。1955‐58年アメリカに、62‐64年にドイツとスイスに留学。国際音楽学会名誉会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ファンタジー放送局89 ROCKETO…
-
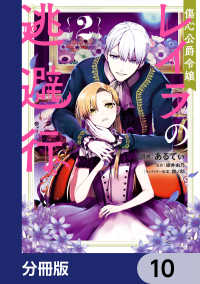
- 電子書籍
- 傷心公爵令嬢レイラの逃避行【分冊版】 …
-
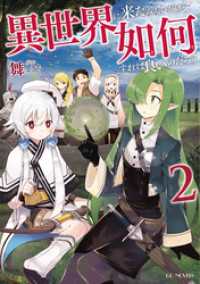
- 電子書籍
- 異世界に来たみたいだけど如何すれば良い…
-

- 電子書籍
- 星のダンスを見においで 宇宙海賊編 創…