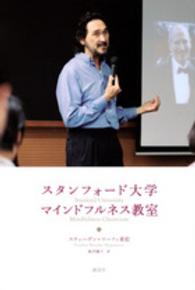出版社内容情報
対位法とは線の書法で、和声法もその流れの中で確立されたという認識を明確に持ち、古今の名曲を対位法的観点によって理解する。
教員養成課程や音楽大学の通年30回の授業で基礎が身に付くように工夫された、はじめての実践的対位法教科書。対位法とは線の書法であり、和声法もその流れのなかで確立された、という認識を明確に持ち、古今の名曲を対位法的観点によって理解する。次に、二声対位法で基礎を修得し、定旋律を用いないさまざまな書法の習熟によって、対位法の骨格を修得する。全体は「定義 → 譜例 → 書法の解説(禁則を含む) → 4~8小節程度の短い練習例題 → 参考実践例 → その解説 → 実習課題(実施はない)」という流れで構成されており、無理なく学習を進められる。第4部では、対位法的手法による作編曲の手ほどきもあり、吹奏楽や合唱指導の現場での活用も期待できる。
はじめに
本書の使い方
本書の特徴
第1部 旋律
第1章 旋律の進行
第2章 旋律とリズム
第3章 旋律と和声
第4章 旋律対旋律
第5章 旋律的楽曲分析
第2部 二声対位法
第6章 1:1(全音符対旋律)
第7章 1:2(二分音符対旋律)
第8章 1:4(四分音符対旋律)
第9章 切分音符による対旋律(移勢対位法)
第10章 混合対位法(華麗対位法)
第3部 定旋律を用いない対位法
第11章 転回音程による二重対位法
第12章 模倣、拡大、縮小、反転、逆行
第13章 カノン
第4部 作曲・編曲への応用
第14章 旋律による修飾
第15章 副旋律
第16章 合唱、器楽アンサンブルのための編曲
本文で示した譜例一覧
【著者紹介】
文教大学教育学部教授。武蔵野音大大学院修了後、ミュンヘン音楽大学に留学。第38回毎日音楽コンクール作曲部門第1位。クラウス・プリングスハイム、田村徹に師事。管弦楽曲、吹奏楽曲、合唱編曲など作品多数。
目次
第1部 旋律編(旋律の進行;旋律とリズム;旋律と和声;旋律対旋律;旋律的楽曲分析)
第2部 二声対位法(全音符対全音符(1:1)
全音符対2分音符(1:2)
全音符対4分音符(1:4)
移勢対位法(全音符対切分音符)
華麗対位法)
第3部 定旋律を用いない対位法(転回音程による二重対位法(転回対位法)
模倣、拡大、縮小、反転、逆行
カノン)
第4部 作曲・編曲への応用(旋律の修飾;副旋律;合唱・器楽アンサンブルのための編曲)
実習課題実施例集
著者等紹介
柳田孝義[ヤナギダタカヨシ]
1948年札幌市生まれ。武蔵野音楽大学、同大学院でクラウス・プリングスハイムに作曲を師事。大学院修了後ミュンヘン音楽大学に留学し、ハラルド・ゲンツマーに作曲を学ぶ。第38回日本音楽コンクール作曲部門第1位作曲賞。第52回、第54回文化庁芸術祭優秀賞。2006年第1回F.Ticheli国際作曲コンテスト(ニューヨーク)第3位入賞。現在、文教大学教育学部教授、武蔵野音楽大学非常勤講師、日本電子キーボード音楽学会代表幹事、日本音楽著作権協会正会員、日本現代音楽協会会員、日本作曲家協議会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。