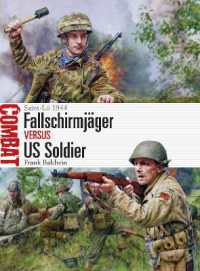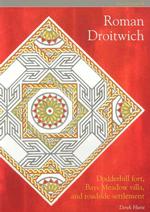出版社内容情報
唱(うた)いながら和音を身に(耳に)つけていく。ソルフェージュの多角的な実践を通じて、和音を身につけるための課題を実習。
「和音について楽典で習ったけれど、音の響きとしてははっきりと捉えられていない」 と感じている人のために、そしてもちろん和音や和声が好きな人たちに向けて書かれた「唱(うた)いながら和音を身に(耳に)つけていく」本。
本書では、ソルフェージュ実技の多角的な実践を通じて和音を身につけます。そのためのエクササイズとして以下を実習します。ヨーロッパ音楽の伝統である「和音数字」に従って、バス音も含め、例えば「ドーミーソー」のように下から上へ(低い音から高い音へ)唱う「和音唱」の実習。実作品の名曲を唱ったり弾いたりする実習。和音数字、コードネーム、和音の種類も学習します。
第1部では「三和音」、第2部では和音外音(和音に含まれない音=旋律的な音)、第3部では七の和音を実習します。第4部では「三和音」を中心とした「鍵盤和声」を扱います。第1部と第4部は連動して実習することも可能です。
はじめに
本書の使い方
入門編 ◆ 本書で身につけたいこと
1 本書で身につけたいこと
2 和音を要約する
3 和音の種類を認識する
4 コードネーム
5 和音数字
6 和音の機能
第1部 ◆ 三和音
7 長三和音・短三和音
8 三和音の和音数字
9 増三和音
10 減三和音
11 三和音の和音数字 まとめ
12 長調の音階と三和音
13 短調の音階と三和音
14 旋律短音階上行形の第6音を含む和音
15 ナポリの6
●コラム 教会旋法
第2部 ◆ 和音外音
16 和音外音の概説
17 経過音、刺しゅう音
18 掛留音
19 倚音
20 先取音、逸音
21 和音外音の復習
第3部 ◆ 七の和音
22 七の和音の概説
23 七の和音の和音数字
24 属七の和音
25 属七の和音アンソロジー
26 長七の和音
27 短七の和音
28 減五短七の和音
29 長調での同主短調の借用
30 属九の和音
31 減七の和音、導七の和音
32 増6の和音
33 和音数字+7
第4部 ◆ 鍵盤和声の入口
34 4声体の和声
35 和音を数字とコードでつかむ
36 和音数字5と46の連結テクニック
37 和音数字6の扱い
付録
名曲和音唱アンソロジー
和音数字一覧表
市川 景之[イチカワ カゲユキ]
著・文・その他
内容説明
和音について楽典で習ったけれど、音の響きとしてははっきりと捉えられていない!と感じている人は多いのではないでしょうか。和音やそのつながりが紡ぎ出す「和声」を、色彩や表情の美として捉え、“喜び”として感じてみませんか。
目次
入門編 本書で身につけたいこと(本書で身につけたいこと;和音を要約する ほか)
第1部 三和音(長三和音・短三和音;三和音の和音数字 ほか)
第2部 和音外音(和音外音の概説;経過音、刺しゅう音 ほか)
第3部 七の和音(七の和音の概説;七の和音の和音数字 ほか)
第4部 鍵盤和声の入口(4声体の和声;和音を数字とコードでつかむ ほか)
著者等紹介
市川景之[イチカワカゲユキ]
1993年東京藝術大学作曲科卒業後、パリ国立高等音楽院に学び、高等和声法、対位法、フーガとソナタ、管弦楽法の各科を一等賞にて修了。エコールノルマル音楽院室内楽科(歌曲ピアノ)修了。1999年帰国。北村昭、島岡譲、永冨正之、佐藤眞、野平多美の各氏、フランスではJ.C.レイノー(和声)、J.C.アンリ(対位法)、T.エスケッシュ(フーガ)、M.ビッチュ(アナリーズ)に師事。国立音楽大学客員准教授、東京藝術大学、洗足学園音楽大学の非常勤講師を務める(ソルフェージュとエクリチュールの両分野)。またフランス歌曲のピアニストや解釈指導者としても活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。