内容説明
東日本大震災から10年へ、被災者のこころの復興に向けて。被災地復興から地域再生へ。震災前のライフヒストリーと、震災後の想いについて、被災者の語りに焦点を当て復興に向かう人々の姿を記録。
目次
序章 震災復興と被災者の“生”
第1章 なぜ「生きがい」を問うのか
第2章 「生きがいとしての農業」という選択
第3章 復興期の“生”への支援―「生きがい仕事づくり」の現場から
第4章 地域社会における共同関係の形成―被災地復興から地域再生に向けて
第5章 なぜ「生きがい」が問われたのか
終章 被災者の“生”の復興に向けて
付録
著者等紹介
望月美希[モチズキミキ]
1990年静岡県静岡市(旧清水市)生まれ。2019年東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻博士課程修了。博士(環境学)。現在、独立行政法人日本学術振興会特別研究員PD(上智大学)、明星大学・中央大学・専修大学兼任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たばかるB
15
原本は博士論文。地域社会学会奨励賞。被災地の取材を通じた生きがい=「その人の生活に組み込まれてきた活動ないし行為から得る、その人が生きていく上での生存理由」(神谷)の実態を提示する。さらに政治哲学上の命題<公共性>対<私的なもの>に対して切り込み私的なものの中での<尊厳ある生>を取り上げている。復興支援などで安心・安全な生活は戻った、しかし何かが失われている。この感覚への違和感が本書に通底している気がする。◆本書1章を通じて、日本内文脈における言論の政治学→人類学or倫理学のパラダイム変化を感得した。2023/02/06
tfj
1
震災から10年が経ち、震災の現場では復興の対象はハードからソフトに移っている。住居や道路が新しくなり、生活インフラが強化された移転地での生活は「便利」になったかもしれないが、利便性は特に高齢者から「すること」を奪ってしまった。居久根や畑の世話など、側から見たら面倒に見える雑務も何十年と続けてきた生活の一部であり、「すること」が減り何かに没頭できる時間が短くなったことで、張り合いが失われてしまった。 生きがいは個別的・能動的な概念であり、行政による画一的な支援や、外から与える支援では<私>に届かないのだ。2021/04/04
-
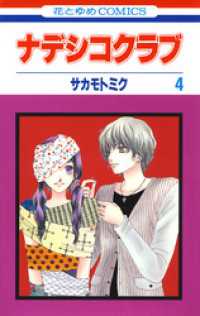
- 電子書籍
- ナデシコクラブ 4巻 花とゆめコミックス
-

- 和書
- 資金繰の経営学







