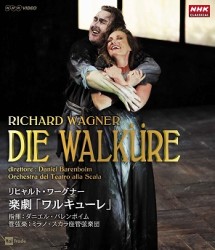内容説明
ファシズムと群衆の関係を論じて、ドイツの思想界に一石を投じたエリアス・カネッティの『大衆の力』から四十年が経った。ポスト・モダンのIT社会において、近代市民社会の主権者であった「大衆」はどこに向かっているのか?一昨年『人間界の規則』でドイツに一大論争を引き起こしたスローターダイクが、ホッブス、スピノザ、ニーチェ、ハイデッガーを結ぶ「主体性」論の系譜から、影の近代史としての「大衆」の歴史を再構成していく。
目次
1 人間の黒さ
2 概念としての侮蔑
3 二重の傷
4 人類学的差異について
5 大衆におけるアイデンティティー:無関心=非差異性
著者等紹介
仲正昌樹[ナカマサマサキ]
1963年広島県生まれ。1989年東京大学教育学部教育学科卒業。1996年東京大学総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程修了(学術博士)。現、金沢大学法学部助教授。専攻は社会思想・比較文学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
34
大衆社会は20世紀の至る所で起こっているためオルテガだけではないのは道理ですが、違う系列の大衆批判論を初めて読みました。しかもドイツ語圏のため対象はヒトラーです。大衆による「下」への凝集力を批判するだけではなく、それを批判する知識人もまた訴える先は大衆であり、その警句は程よく大衆に受ける大衆批判ではないのかというメタ大衆批判が本書の特徴です。大衆と大衆批判に埋没しない真理というのは反知性主義的な構造を持っており、かなり際どい議論です。ローティにも言及があり、いわゆる冷笑主義という批判に遭うやつです。2021/05/15
羽生沢
2
「下」への強制的同質化へと向かう大衆社会を痛烈に批判した書。著者の立場としてはニーチェやカネッティに近い。群れて異端を潰しにかかる大衆の平等主義に対して、他者の芸術的な優秀さを認め「称賛」する行為に活路を見出している。2015/04/29
-
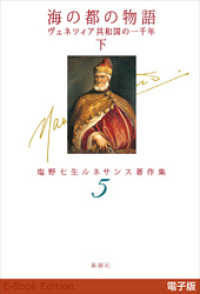
- 電子書籍
- 海の都の物語 ヴェネツィア共和国の一千…