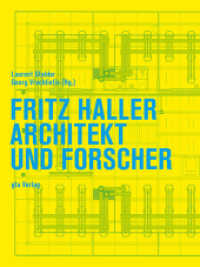目次
第1章 はじめに―自分の頭で考えるということ
第2章 「考える」かたち
第3章 「考える」能力はどのように生まれ、進化してきたか?
第4章 生物の生理構造
第5章 考える手段としての言語
第6章 言語の始まり―記号化
第7章 検証―「考え」の確認
第8章 立案―「考え」の開始
第9章 むすび
著者等紹介
大須賀節雄[オオスガセツオ]
1957年3月東京大学工学部卒業。4月富士精密工業株式会社入社。1961年1月富士精密工業株式会社退社、東京大学助手(航空研究所)。1967年2月東京大学助教授(宇宙航空研究所)。1981年4月東京大学教授(工学部境界領域研究施設)。1988年4月東京大学教授(先端科学技術研究センター)。1995年3月東京大学を定年により退官。4月早稲田大学教授(理工学部)。2000年3月早稲田大学大学院客員教授(理工学研究科)。2003年3月早稲田大学退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
YNR
0
思考について論理的にアプローチされている。考えるとは、心のなかに、ある概念を形成する行為である。まずは、「考える」かたち(立案と検証)を見つけること。保守的な考え方と、脱既存概念の考え方。新しい視点をつくることは、まずは心的な準備が必要である。美の間隔が創造という行為に大きく関わっていると信じている。2016/06/15
明るいくよくよ人
0
考えるという構造を科学的に考えた大家の本。脱既存概念が目指すところだが、そこに至る確実なメタな方法論はない。最後は、考える人の美意識のみがこれを決する場合もある。言語と生理機構、言語と考えることに関してよく整理されていて、自分にはためになった。2012/04/04
takao
0
ふむ2025/05/14
ゆう
0
いけた。思考ってなんだ?と思い続けて色々読んできたが読み終えて数時間呆然としていた。閃きによりパラダイムシフトが起こってきたこと、また、閃きはCPUにはできないことからシンギュラリティは暫く起こらないなと思った一方でこの考え自体もこの本でいう脱既存概念していない固定的な思考なんだろうなというジレンマを感じた。あと「良いものは美しい」という命題も強く印象に残ったし、パースのアブダクションもひらめきの一部でしかない。生物のニューラルネットワークも高性能すぎることも初めて知ったし、諸々衝撃的だった。2020/07/21
ゆう
0
いけるやろと思ったがバチクソ難しい。。2020/07/20