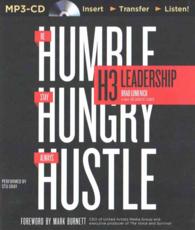- ホーム
- > 和書
- > コンピュータ
- > プログラミング
- > SE自己啓発・読み物
目次
第1章 はじめに
第2章 Ruby
第3章 Io
第4章 Prolog
第5章 Scala
第6章 Erlang
第7章 Clojure
第8章 Haskell
第9章 全体のまとめ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fseigojp
7
懐かしいprologの解説があった 土人と宣教師の川渡り問題などが実にエレガントにかけるのに感動した一昔前2015/07/17
もりけい
3
オブジェクト指向万歳と思いながら過ごしてきましたが、関数型プログラミングも目にするようになり、Scalaをかじってみるとこれまた万歳なわけです。そんな折りいろんな言語があるだろうと思って手にした書籍です。Prologってアルゴリズム考えなくても数独が解けるんですよ。もう魔法です。一つの言語パラダイムだけでプログラミングしてると思考の柔軟性が妨げられますが、そんなパラダイムを効率よく知ることのできる稀な書籍です。JavaやC++しか知らない人に読んでもらいたいです。2014/09/21
オザマチ
3
Prologで数独を解く奴はビビッときました。手続き型言語と考え方がまるで違って面白い。2014/08/01
Uzundk
2
こんなに多様な言語があり、言語毎に抽象化の度合い背景の思想があることを知らなかった。それぞれの差異がとても興味深い。特に気になったのは事実とルールを記述して結果を推測させるProlog。解を得るためのロジックを組むことがプログラミングだと思っていたので驚いた。後から考えればマシン語に直すのが主眼では無く"どのような抽象化を行うか"が本質であると気が付き納得がいった。抽象化の仕方によって新たな抽象化が発達し、あることが簡単にでき、またあることが難しくなる。とても面白い世界が広がっていることを知った。2015/03/19
ますみ
2
7つの言語パラダイム・コンセプトを見学していく本。クラス・プロトタイプ・ユニフィケーション・アクター・コルーチン・マッチング・モナド… と色々なプログラミングパラダイム・計算概念に出会えます。 プログラミング言語論と計算機科学をもっと勉強したくなります。2012/05/28



![シルバニアファミリー ポストカードブック [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40652/4065290503.jpg)