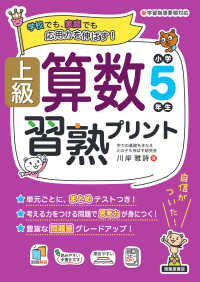- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
内容説明
本書は、歴史ずきの子を育てるために適当と思われる50篇の歴史物語を選び、日本歴史の大きな流れがわかるように構成しています。しかもひとつひとつのお話の間に、親子の会話に必要と思われるアドバイスを盛り込み、語りあいながら歴史を学べるように工夫された“お話し日本歴史”です。
目次
日本のあけぼの(ゆるやかな発展の原始の時代;採集の社会から農耕の社会へ;階級の発生と国家のめばえ)
貴族の時代(貴族の支配がつづいた時代;辺境の民と異民族;貴族と武士)
武士の時代(武士が勢力をのばしていった時代;民衆の力の高まり;ヨーロッパとの出会い;武士の支配が確立した時代;天下の台所―大阪;庶民の文化)
新しい時代(富国強兵と民主主義;欲しがりません勝つまでは;侵略の15年)
わたしたちの時代(平和と民主主義への問いかけ;経済の高度成長と生活の変化)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新父帰る
5
1989年8月刊。庶民の視点から見た歴史話である。その多くを『おはなしr歴史風土記』全47巻(岩波書店刊)を種本としている。正直私の知らない沢山の用語が出て来て大変為になった。勿論、著者の歴史観には抵抗があるのも正直なところであるが、歴史は全方位から見るのも大事だと思うので手にしてみた。本書のタイトルを少し引用してみよう。「税負担の重さ/奈良の大仏」「田村麻呂は英雄か」「オホーツク人と擦文人」「百姓の勝どき」「コシャマインの戦い」「キリスタンがり」「ワタにうずまる村」「糸ひきの歌(野麦峠)」等々である。2023/12/16
がんぞ
4
大作『おはなし歴史風土記・全47巻』、他(岩崎書店)から、“考える学習”の材料として50本(各1〜2頁)を選び解説したもの。1.戦前は「1万年以上前に列島に人は居なかった」常識で関東ローム層にあたると発掘を止めたが、相沢忠洋‥13「たたり火のなぞ」では正倉(税として集められたコメを蓄えた倉庫)が度々火事にあったのはなぜだろう?「放火ではなかったか」/34学制発布から5年間で2万5千の小学校、就学率4割‥36輸出の1/3は絹糸‥39飢餓の島ガダルカナル‥43、終戦の年11月上野駅で1日平均2.5人餓死屍体‥2016/11/05