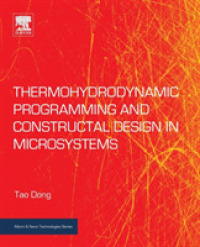- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
出版社内容情報
目次
<第1巻第3分冊>
第5篇 絶対的および相対的剰余価値の生産
第14章 絶対的および相対的剰余価値
第15章 労働力の価格と剰余価値との量的変動
第16章 剰余価値率を表わす種々の定式
第6篇 労賃
第17章 労働力の価値または価格の労賃への転化
第18章 時間賃金
第19章 出来高賃金
第20章 労賃の国民的相違
第7篇 資本の蓄積過程
第21章 単純再生産
第22章 剰余価値の資本への転化
第23章 資本主義的蓄積の一般的法則
第24章 いわゆる本源的蓄積
第25章 近代植民理論
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おたま
34
この第3分冊で、『資本論』の第一巻を読了したことになる。マルクスが生前に刊行したのはこの『第一巻』だけだった。この『第一巻』の中に、その理論的な中核となる考えはほぼ出揃っているようだ。第3分冊での中心は、資本主義的蓄積(生産手段が次第に高度化していき、資本の配分が労賃よりもそちらに比重をかけていく)とそれによって生成してくる相対的過剰人口(失業者、半失業者(今でいう非正規雇用等))について述べたところ。そしてもう一つは本源的蓄積について述べたところ。特に後者は第一巻の締めくくりともなる部分であり、圧巻!2022/06/01
Nobu A
13
カール・マルクス著書(翻訳版)3冊目。資本論全巻読了。と言うと聞こえは良いが、正直最後の最後まで一知半解。そもそも第1巻から挫折。続巻が埃を被って書架に長年鎮座していたのに一種の慚愧の念に堪えられず、手に取った次第。通勤電車とバスの中で流し読み読了。最初から十分に理解していないとそうなるよな。いつか再読。読書会の課題図書にでもなれば気合を入れて読むだろうな。やはりこの手の本は博学の人の解釈でも聞いたり他人と議論したりしないと咀嚼できない。独りで気楽に読める本じゃない。少なくとも今の私には。言い訳ばっかり。2025/06/05
tharaud
9
第一巻読了。難所と言われる冒頭の「商品」を乗り越えてしまえば意外と歴史的な分析が多く、社会への怒りと我慢強さがそれなりにあれば読み通せる。とくに後半は、資本家たちやそのお抱え学者と見做した者たちへのパンチの効いた皮肉を堪能した。ジェレミー・ベンサムは「『筆とらぬ日はなし』をモットーにしたこのけなげな男は、こんながらくたで自分の山なす著書を充満させたのである」、エドマンド・バーグは「この追従屋」「どこまでも平凡なブルジョア」など。20世紀最大の影響力を持った著作がこんな罵詈雑言で溢れているのは愉快でもある。2024/10/13
ちゃあぼう
5
(1)(2)と同様に難しいのは承知で読んでみたが、予想通り、ほとんど理解できなかった。同じ単語が何度も出てくるのが、かえって分かりづらかった。それでも、「マルクスの資本論」を読んだことは、良い経験になり、読書歴に拍がついた気になれた。2017/11/10
浅井秀和 「不正規」労働者
4
マルクスは本源的蓄積の章までは、資本主義の内在的法則を原理的に解き明かしていく。前貸資本に生産手段である不変資本を可変資本である労働力を売るしか ない生産手段を所有しない労働者が使用して不払労働である剰余価値の発生がなぜ生まれるのかを理論的に、もしくは「労働日」という実例報告をあげて解明し ていくのであるが、「本源的蓄積」は、原理的に見れば「前貸資本」は、直接生産者への「収奪」であることを、「歴史」として「証明」する。その典型的国家 はオランダである。2015/01/08
-

- 電子書籍
- 研修医のための内科診療ことはじめ 救急…
-
- 洋書
- East