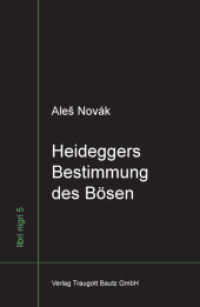内容説明
世界的に著名なマルクス主義歴史家E.J.ホブズボームが論じたナショナリズムの歴史と現在。ナショナリズムはいかなる歴史的・思想的な背景のもとで生まれたのか?それは、国民国家の形成や民族解放運動の展開にどのような役割を演じたのか?ボーダーレスの時代といわれる21世紀におけるナショナリズムの命運は?ナショナリズムをめぐる様々な論点を世界史的な視野で解きほぐした本書は、国家=民族=国民が一体化しがちな日本人の意識にも反省をうながす内容をもっている。
目次
第1章 新機軸としてのネイション―革命から自由主義へ
第2章 大衆的プロト・ナショナリズム
第3章 統治者側の見方
第4章 ナショナリズムの変容―1870‐1918年
第5章 絶頂期のナショナリズム―1918‐1950年
第6章 20世紀後半におけるナショナリズム
著者等紹介
ホブズボーム,E.J.[Hobsbawm,E.J.]
マルクス主義歴史家
浜林正夫[ハマバヤシマサオ]
1925年北海道生まれ。1948年東京商科大学(現一橋大学)卒。現在一橋大学名誉教授
嶋田耕也[シマダコウヤ]
1948年北海道生まれ。1978年東北大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在秋田経済法科大学経済学部教授
庄司信[ショウジマコト]
1958年山形県生まれ。1993年一橋大学大学院社会学研究科博士課程中退。現在秋田経済法科大学経済学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
58
1985年の講演に、その後の激動を受け1992年に第6章を書き直したもの。実に博覧強記な著者らしい書きっぷりで、『想像の共同体』などの成果を織り込みながら(しばしばナショナリズムをそのように表記して説明している)、主に19世紀以降のヨーロッパ史をベースに、ナショナリズムの出現と盛衰を、国家の統一や分離運動などとの関係を中心に論じている。イデオロギーとしてのナショナリズムが先行して体制が変わるケースは皆無で、事後かせいぜい体制が変わる過程で出現するという見方は妥当と思う。ラテンアメリカへの評価には疑問も。2024/09/09
馬咲
6
西洋を中心に、およそ19世紀末~20世紀半ばまでの「ナショナリズム」概念の意味内容の変遷を分析。諸集団の統合を通してネーションの規模拡大を目指した自由主義的ナショナリズムから、エスニシティや言語を基準に集団の分離・純化を志す民族主義的ナショナリズムへ、というのが大筋の変容。この見立ての上で、各時代、各地域の利害集団の多様な実態をつぶさに捉え、理論と現実のギャップに注意した該博な叙述を展開している。現実の体制変化に直面して新たな集団形成の意識が生じるのであって、その逆ではないことを、様々な事例を通して示す。2024/12/22
シュークリーム・ヤンキー
3
ゼミで読んだ。世の中で起きてきていることを「それはナショナリズムだ」と片づけてしまうことは簡単だ。しかしナショナリズムって一体何なのだろうか。本書はそれを、数世紀に渡る世界各地の事例をダイナミックに俯瞰しながら論じる。グローバル化の進展とともにナショナリズムは廃れていくだろう、というのが筆者の見通しだ。しかし出版から30年が経た今を見ると、ナショナリズムという想像は、筆者が思っていたよりもずっと深く、人々の心を支配しているのだと感じる。2018/11/19
ドウ
1
ナショナリズム論における近代主義者の本だが、反近代主義も踏まえて議論を展開しているように思える。「3つの革命(環大西洋革命)」期のナショナリズムをもたらしたのは宗派や帝国に基づくプロト・ナショナリズムであり、そのネーションは支配からの解放と統一に基づいていたのに対し、イタリアやドイツの統一を経た19世紀~20世紀前半はナショナリズムが変容し、言語やエスニシティがナショナリズムの構成要素として重大になったとする。20世紀後半の第三世界の独立時には言語やエスニシティとは真逆で再び英米仏時代のものになった。2015/05/08
ローマ奏者
0
『ナショナリズムの發明』という書名に替えるでもいいと思う。ホブズボームの1992年に作った預言はせいぜい半ばを的中するというところだ、だってナショナリズムは大国間の角力で消えていくといっても、国内政治での出演の時間がどんどん増えている。この信仰を欠く時代にナショナリズムという幻想は不可欠だからだろう。2022/03/25


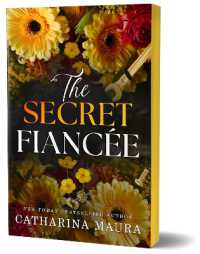
![L'amore di Dio è per tutti : la passione per l'evangelizzazione ([I papi del terzo millennio] 149) 〈149〉](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)