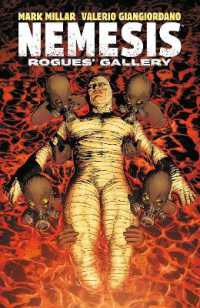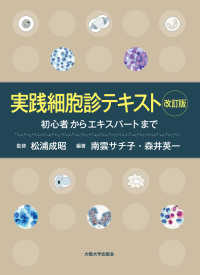- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 学習
- > 文明・文化・歴史・宗教
目次
はじめに―江戸時代の子どもたちは?
手づくりのおもちゃ
おみやげとだいすきな凧
読むことと書くこと
遊びなかまとみそっかす
子どものお祝いとお赤飯
大人のまねと、おまじない
着ているものと住んでいるところ
だいすきな食べもの
おかしのいろいろ〔ほか〕
著者等紹介
加藤理[カトウオサム]
1961年生まれ。東京成徳大学子ども学部教授。日本子ども社会学会理事、BPO(放送倫理・番組向上機構)青少年委員会委員。日本児童文学学会二十五周年記念論文賞(1988年)、日本児童文学学会学会賞奨励賞(1997年)受賞
石井勉[イシイツトム]
1962年生まれ。画家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
itokake
10
語り手は佐々木門之助くん12歳、江戸時代終わりごろの武士の子供。朝起きると、「おめざまし」に甘いお菓子を食べるというエピソードがあるが、祖母が私の母に同様のことをしていたのを聞いたことがある。解説はなかったが、こういう風習があったのだろう。江戸時代、1日2食から3食になったが、その理由が「飢饉のために一度に十分な量を食べることができず、もう1食食べざるを得なくなった」とあるが、しっくりこない。照明としての菜種油が普及し、人々の活動時間が増えたという話の方がわかりやすい。きっといろんな説があるのだろう。2022/01/25
ツキノ
2
図書館新着本。まずは江戸時代を借りてみた。子どもにスポットを当て、子どもの目を通して当時くらしがわかる。こういう本こそ、図書館には必要。2012/01/27
紅独歩
0
江戸時代に生きる少年の絵日記風モノローグから、当時の習俗や社会情勢がうかがえる仕組みの絵本。淡々とした調子がかえってリアルで面白い。凧コレクターで『凧ぐるい』という渾名であるとか、文字の読めない幼少期に「北斎漫画」を見せると機嫌が直った、等こまかいエピソードが良い感じ。飢饉によって、一日の食事が二回から三回になった(一度の量が少ないので)という説は目からウロコ。2012/04/19
-
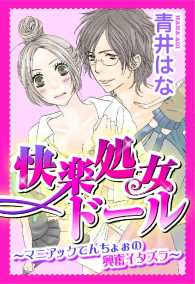
- 電子書籍
- 快楽処女ドール~マニアックてんちょぉの…
-

- 和書
- 民事訴訟法 (第7版)