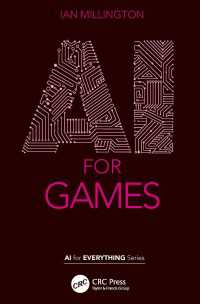出版社内容情報
76万PV*を記録しネットで話題沸騰の「ファシズムの体験学習」を紹介しつつ、ファシズムの仕組みを解説。ナチスの大衆動員の実態、ヘイトスピーチなど身近な問題も論じる、全く新しい入門書! *『現代ビジネス』記事https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56393
内容説明
ウェブ上で話題沸騰のナチスを体験する授業を通じて、ファシズムの仕組みに迫る。ナチスの大衆動員の実態から、ヘイトスピーチなど身近な問題まで論じる、民主主義のための新たな入門講義。
目次
第1章 ヒトラーに従った家畜たち?
第2章 なぜ「体験学習」なのか?
第3章 ファシズムを体験する
第4章 受講生は何を学んだのか?
第5章 「体験学習」の舞台裏
第6章 ファシズムと現代
著者等紹介
田野大輔[タノダイスケ]
1970年生まれ。甲南大学文学部教授。専攻は歴史社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
97
著者が甲南大学の授業で行ってきたファシズムの体験学習(いまは休止状態)。受講生は体験学習で集団の力の実感、責任感の麻痺、規範の変化を学び、「権威に服従することで、人々は他人の意思を代行する『道具的状態』に陥る。だがそれは同時に、彼らが自分の行動に対する責任から解放され、敵や異分子を思うまま攻撃する『自由』を得ること」を実感する。体験型授業では制服とシンボルマークを身につけ、実演する。やり過ぎの感は否めないが、そのことを理解して行っているのだから、徹底している。→2023/06/12
harass
92
気になっていた本を借りる。途中で気がつくがこのドイツ学者だったか。甲南大学で10年近く行われてきた著者の講義、ファシズム実習の様子や狙い意図と、最近のナチ研究のことなどがまとめてある。集団で規律正しく、声を張り上げ、「敵」を排斥、画一的なユニフォーム、白いシャツとジーパン、シンボルのワッペン、上からの命令であるから、自分たちは無責任になれるという、ファシズムの薄ら寒さを体験させる。戯画的なナチスの真似をすることで、学生に演技であると意識できるが、無意識の日本のファシズムまで揺さぶれればいいが。良書。2021/07/14
1959のコールマン
83
☆5。良くあるファシズム、全体主義の解説本ではない。体験学習もそうだが、加えて最新の研究も載せているので、勉強になる。最近の研究ではナチズムは「合意独裁」と見る視点が一般化しているとのこと。また、アイヒマンはアーレントのいう「悪の陳腐さ」といった凡庸な小役人ではなく、筋金入りの反ユダヤ主義者で、確信的なナチスであり、ユダヤ人の虐殺にその自身の卓越した組織力と創造性を十二分に発揮した人物で、エルサレムの裁判で見せた卑小な姿は、死刑判決を免れる為の演技だったとのこと。ふむふむ。2021/05/05
アナーキー靴下
81
ナチスや心理実験等の研究、考察を踏まえ、ファシズムの体験授業を実施した著者が、その過程を記した本。集団行動による意識の変化は「集団の力の実感」「責任感の麻痺」「規範の変化」の3つ、という考えは頷けるものの、集団心理がシームレスにファシズムに直結するような、論理の粗さを感じた。集団心理が危険、だけでは「アイロニカルな没入」層を増やすだけだ。ファシズムに到達するには、不満や抑圧等、強いストレスが不可欠だと思う。良いときには力の源にもなる集団心理の危うさと、個人が外的圧力から受ける影響は切り分けて欲しかった。2021/02/27
おたま
79
田野大輔が勤務する大学で、2010年から10年間行われたファシズムの体験授業の記録と考察。マスコミでも報道され知られるようになった。年間に2コマの時間を使って大学の教室内に疑似ファシズム状態を作り出す。参加学生250名程に、「ハイル、タノ!」と叫ばせ、一体感を伴う行動(例えば全員での足踏み等)をさせ、ユニホームとなる白シャツと青いジーパンを着用せたりする。クライマックスは参加者全員で、学内のベンチでいちゃつくカップルを取り囲み「リア充、爆発しろ!」と叫んで、追い立てること。(カップルは依頼したサクラ)2022/12/07