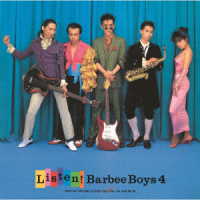出版社内容情報
冷戦後の世界秩序の変化に対応できなかった矛盾が噴出する3・11後の日本社会。この間デモや社会運動、政治に様々に参与してきた私たちの経験を戦後史のなかで叙述し、社会を変える力と協働の足場を解明した意欲作。
内容説明
政治学者こたつぬこ先生が、ポジティブに政治と社会運動を語る!
目次
第1章 安倍政権とは何者か(ミネルヴァの梟は迫りくる黄昏に飛び立つ;引き裂かれていく二つの顔;「非常識」な支配 ほか)
第2章 私たちは戦後をどう生きてきたか(戦後七〇年の社会運動の遺産と負債;日本の社会運動は本当に「弱かった」のか;「戦後」はどこからはじまったか ほか)
第3章 3・11後の社会運動と日本のかたち(3・11後の社会運動はなにを変えたのか;3・11後の社会運動は政治を変えたのか;若者は保守化したのか;「日本のかたち」が変わる)
著者等紹介
木下ちがや[キノシタチガヤ]
1971年徳島県生まれ。政治学者。一橋大学社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(社会学)。現在、工学院大学非常勤講師、明治学院大学国際平和研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
41
「立憲主義」という唱えでは、こうした人々の「実定憲法以前に備わる憲法意識」をつかまえることはできません。同時にこれまでのような日本人アイデンティティに凝り固まった訴えもまた、とりわけ若い世代に届くことは決してないでしょう。女性や若者にとって、そして移民や外国人にとって、日本国憲法はいまだ「手に届かないところに高く掲げられた理想」にほかならないのですから。/構成がしっかりした簡潔な素描になっていると思いました。安倍政権なんで続くのか~とか今の若者は~なんて方にお勧めだと思います。2019/04/19
小鈴
16
挫折。現状の解説が自分に合わない。読んでいて単純に面白くない。タイトルと中身にギャップがあるよね。タイトルの答えは本書には書かれていません。運動論史の本なのですが、片方しか書かれていないんですよ。日本会議の運動は運動参加者から見たら「社会を変えた」成功事例ですよね。彼らほど熱心に社会を変えるために活動している人達もいないですよ。彼らの社会変革運動についてスルーしている時点で、社会を変える人達の「人間像」にバイアスがあるわけです。運動は左翼や反権力だけのものではない。2019/06/06
バーバラ
9
Twitterでフォローしている"こたつぬこ"先生の本。Twitterではちょっと偏ってる面もあるけれど、この本は至極穏やかで戦後民主主義と市民運動の歩みを平易な言葉を用いて読み解いてあり、政治クラスタでなくても読みやすい。安倍長期政権において戦後日本が守ってきた日本国憲法を支えとする平和な社会は今未曾有の危機にある。守るべきものを守るためには自分も変わろう、社会を変えよう。大それたことをしなくてもいい。自分のできることを地道に少しずつしていけばいい。そういう前向きな気持ちにしてくれる1冊。2020/08/04
Sym
6
めちゃくちゃ面白い。 同世代の若者の見方が特に良かった。 「若者の保守化」と言われているけど、「社会運動をやる側も、若者や学生がもつ潜在的な政治的社会的意識に鈍感なままであることが大きな要因」という視点大事だな。 あと、沖縄あつい!!!泣きそうになった。泣いた。「変わらないためには、変わらなければならない」2019/06/16
Eiki Natori
5
「安倍政権はこんなに酷いのに倒れない」のか。 それは「酷いから倒れない」もしくは「酷くなればなるほど倒れない」という切り口から進む本。 問題を先送りにし、反対派を切り崩し、「代わりがいない」と世論を無力化して、不人気なのに長期化する安倍政権。 冷笑派は「運動では何も変わらない」という。でも社会運動が何をもたらしてきたか、ポピュリズムとは何か。前作より、わかりやすい内容にされた本。2019/04/28