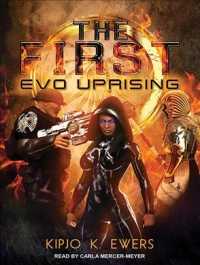出版社内容情報
「日本の食」の問題に取り組み、そして支えてきた生活クラブ生協の40年間。
今の日本では、次から次に食の安全を真剣に問い直すべき事件が起きている。安価で安全なものが確実に確保できることこそ、人間の生活の基本でなければならない。一方、現在の日本の食料自給率はわずか41%、これは先進工業国の中で異常に低い数字である。豊かな自然に恵まれた日本は、なぜ「安全な食」を「自前で作る」ことを忘れてしまったのか。その問題に取り組み、ひとつのあるべき方向性=具体的解答を示してきたのが、「生活クラブ生協」である。食の安全、自給率アップ、環境問題など、様々な問題に生活クラブ生協はどのように行動してきたのか。本書は、団体の活動記録ではなく日本の食はどうあるべきかを根源的に問い、最終的に「誰もが暮らしたい社会」をつくりたい、という理想までを語る、示唆に富んだ農業論であり、ユニークな消費者論でもある。
目次
第1章 生活クラブ生協を知るキーワード―「共同購入」「消費材」などの先見性(そうあってほしい社会へ向けて;こんな時代に最初の一歩が始まった ほか)
第2章 生活クラブ生協の実力―結ばれた消費者と生産者(すべては牛乳から始まった;お金しか見えない市場経済に人間の顔を―「生産する消費者」運動 ほか)
第3章 なぜ「食の自給」の旗を立てたか(食をめぐる大変革の時代がやってきた;幕を開けた、地球規模の食料争奪の世紀 ほか)
第4章 「遺伝子組み換えにNO!」を掲げた(「遺伝子の組み換え」の本質とその重要性;遺伝子組み換え作物が日本へやってきた ほか)
第5章 未来へ向ける生活クラブ生協の希望(「食料自給率」の数値からこぼれ落ちるもの;特定企業による「種」の独占状態に対抗する ほか)
著者等紹介
河邑厚徳[カワムラアツノリ]
映像ジャーナリスト。1948年生まれ。東京大学法学部卒業後、NHKに入局。主に歴史、文化、宗教などの教養番組を担当し、「シルクロード」「加藤周一・日本その心とかたち」「アインシュタイン・ロマン」「チベット死者の書」「インターネット・ドキュメンタリー地球法廷」「エンデの遺言」「世界遺産関連特集」「テレビ放送50年企画・未来への航海」など、数々の特集ドキュメンタリーを手がける。NHKエデュケーショナル・エグゼクティブプロデューサー
榊田みどり[サカキダミドリ]
農業ジャーナリスト。1960年秋田県生まれ。東京大学大学院地域文化研究科(フランス科)卒。農政ジャーナリストの会幹事。学生時代から、有機農業運動に関心を持ち、国内の農村回りを始める。87年、消費者団体・生活クラブ生協連合会に入職。広報室記者として、食・農業・環境問題を中心に記事を担当。90年よりフリーランス記者。週刊誌など一般総合誌や農業専門誌で執筆を始める。04年度~日本農業賞特別部門「食の架け橋賞」審査員。07年度~農水省「農業体験学習全国定着化推進事業ワーキンググループ」委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
- 洋書
- Mi Dia Par