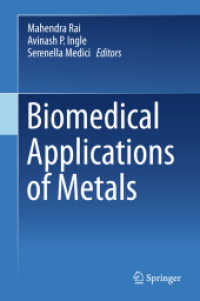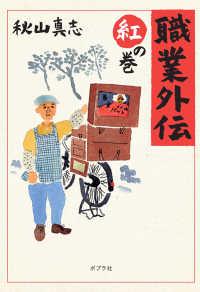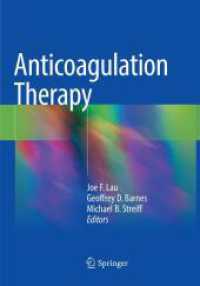内容説明
近現代天皇制研究の泰斗が昭和・平成を軸に「宗教」という視点から皇室の歴史をひもとく画期的皇室論!
目次
プロローグ 天皇は「現人神」となった
第1部 昭和天皇と宗教(若き日の昭和天皇;戦争と祈り;人間に戻った「現人神」)
第2部 平成の天皇と宗教(災害と祈り;生前退位まで)
エピローグ 「平成」終焉後の天皇
著者等紹介
原武史[ハラタケシ]
1962年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程中退。日本経済新聞記者、明治学院大学国際学部教授などを経て、放送大学教授。専攻は日本政治思想史。『「民都」大阪対「帝都」東京』(サントリー学芸賞受賞)、『大正天皇』(毎日出版文化賞受賞)、『昭和天皇』(司馬遼太郎賞受賞)、『滝山コミューン一九七四』(講談社ノンフィクション賞受賞)、『「昭和天皇実録」を読む』『皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。』(三浦しをん氏との共著)など著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
35
大著『皇后考』の着想が簡潔にまとめられており、上手く整理されている印象です。今までに無かった皇室観から考察されているため、語りおろしの文体に似合わず理解するのが難しいはずです。天皇のことを論じているから右翼だろうと思いきや、皇室の呼称の問題や比較文化研究の観点では左翼だろうともいえます。そのどちらとも判断がつかないところに、カトリックのエピソードが盛り込まれています。イデオロギーに囚われないで、皇室の活動が国民に理解され愛されることが、「一君万民」という本当の価値につながるというのが著者の思いでしょう。2019/04/20
樋口佳之
30
神功皇后と光明皇后は、日本史における皇后像の〝二つの原型〟ともいうべき存在/「統治権の総攬者」から「象徴」へと変わったとしても、戦前と変わらない「君民一体」が確保される限り「国体」は護持されると、天皇は確信していた/「改宗問題」は、同じく占領期にくすぶりつづけた天皇の「退位問題」とセットで捉えるべきだと思います。つまり、〝退位を封じられた天皇が、退位に代わる「責任の取り方」として占領期に改宗を考えていた〟というのが、私の見立て/積ん読状態の「皇后考」へのウォーミングアップになったかも。2019/05/20
gtn
12
「現人神」は明治以降に新たに作られたイメージであることを知る。昭和天皇も戦中、忠実にそれを演じた。戦争が膠着するうち、神に向かって御告文を唱えることが増え、次第に合理的思考から遠ざかっていく天皇。そして天皇を利用する取り巻きの妄想と暴走。過てる宗教は一国を滅ぼす。2019/07/23
kenitirokikuti
11
昭和天皇といえば「あっ、そう」を思い出すが、平成天皇は明らかに異なる。雲仙・普賢岳噴火の被害者見舞いから続く被災者の訪問が第一ではないにせよ、あの姿がよく記憶されている天皇の姿だと思われる。あの特に定めにない「公的行為」が平成天皇の思想だった(そして、一歩遅れて皇后がついてゆく)。これは次の「令和天皇」にそっくり受け継がれるわけではないので、それがどのようなものとなるか、そこに注目される。2019/04/27
SK
7
70*『昭和天皇』など、原先生の他の著作との重複が多かったかな。貞明皇后は日蓮正宗の御本尊を所持していたようだが、さすがに潮新書では書けないのかな(笑)。2020/03/07