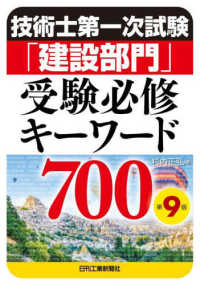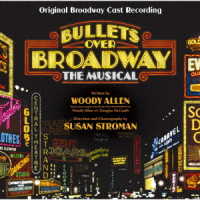内容説明
宗教的考察から、ポロリ事件そしてキラキラネームまで知れば知るほど深遠な大相撲の世界へようこそ!
目次
1章 「神」と共にある世界(土俵という聖域―なぜ大相撲は摩訶不思議なのか?聖域を理解する知性と品性;花道―髪に花をさした力士たち 花道は「霊気」の通り道 ほか)
2章 人間社会とどう折り合う?(一門―日本相撲協会は普通の組織体か!?「貴の乱」と波乱の理事選;横綱審議委員会―協会の言いなりか?女性初の委員誕生の舞台裏 ほか)
3章 くやしかったら強くなれ(番付―実力だけを評価する世界 くやしかったら強くなれ;格差―あらゆる場所に定められる格差 憧れの大銀杏と土俵入り ほか)
4章 時代に応じた離れ技(相撲茶屋―心ときめく異世界への入口 角界を揺るがせた理事長の割腹事件;四股名―キラキラネームの力士たち 今に伝わる四股名の系統 ほか)
著者等紹介
内館牧子[ウチダテマキコ]
秋田県生まれ。武蔵野美術大学卒業。三菱重工業に入社後、13年半のOL生活を経て、1988年に脚本家デビュー。テレビドラマの脚本に「毛利元就」「ひらり」「私の青空」など多数。2000年から10年まで女性初の横綱審議委員会審議委員を務める。06年、東北大学大学院文学研究科修了。05年より同大学相撲部監督に就任し、現在は総監督(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
321
なぜ相撲が国技となったのか? 花道の由来は? 九州場所だけ、横綱が敗れてもなぜ座布団が舞わないのか? 天皇賜杯の裏側に刻まれた製造年が、「大正十六年」。存在しない年号の謎、などなど興味深い「不思議」が提示され、すっきり解答、腑に落ちる。大相撲の奥深さがよく分かった。女性初の「横審」を10年勤め、東北大の大学院や、相撲教習所で相撲の歴史を学んだ内館さんならではの好著だ。世代交代の大波に洗われそうな大相撲。いまこの時期に、読んでおきたい1冊だ、と強く思った。2024/06/13
佐島楓
74
面白かった。面白かったけれど、それは私が大相撲ファンだからそう思うのであって、大多数のかたにはマイナーな情報だろう。究極の実力・階級社会であることや、女人禁制のしきたりを今の時流にそぐわないと忌避されるかたもいらっしゃるのだろうが、そこを緩くしてしまうと大相撲は大相撲でなくなってしまうと私は思っている。ファンほどその思いは強いのではないだろうか。2018/09/18
メタボン
51
☆☆☆☆ 内館氏の相撲に対するリスペクトが半端ない。単なる毒吐きかと思っていたが、きちんと伝統を踏まえての発言に敬意を表したい。相撲の格差社会を垣間見たり、髪に花を挿して入場したから「花道」と呼ばれるようになったこと、手刀は右手で左・右・中と切ることなどを知って、面白かった。また天皇賜杯の大正16年4月29日のミステリーも興味深い。2020/01/06
gtn
42
相撲を愛するあまりに、著作業を中止し、東北大学で相撲史を学び直した著者。「伝統文化や民俗行事、習俗等に関しては、男女共同参画にする必要はまったくない」と断言する。全く同感。相撲は千数百年以上続く日本の文化。世界標準に迎合すれば、日本の文化は消滅する。一点、懸賞金の受取り方についても、著者は「神事」だと見做し、左手で掴む朝青龍を非難しているが、確か手刀を始めたのは戦中戦後活躍した名寄岩ではなかったか。2024/06/13
のびすけ
39
内館牧子さんは2000年から10年まで女性初の横綱審議委員を努める。審議委員を努めるに当たり、東北大学の大学院に入り相撲史を学ぶ。本書はその時に学んだ相撲史をベースに、大相撲の歴史や仕来り、小ネタについてまとめられている。横審時代の裏話や暴露話、「相撲界に物申す!」的な、内館さんならではの話しを期待していたが、そういう内容ではなかった。2020/11/01