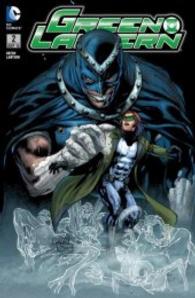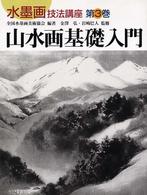出版社内容情報
わが子の吃音は自分のせい、と責めていたり、吃音の子どもとどう接したらいいかわからないという親御さん必読の書!
うちの子、吃音!? そう気づいたら読む本
わが子の吃音は自分のせい、と責めていたり、吃音の子どもとどう接したらいいかわからない親御さんに読んでほしい、吃音の人の思いが詰まった一冊。専門家のアドバイスも。
どうやって、吃音を軽くするか、という専門書はたくさん出ているが、親御さんの知りたいことは、「この先、うちの子はどうなっていくのか」「どう接して、いったらいいのか」ということ。小・中・高・大学生、社会人、専門家、そして、吃音の子どもをもつ親たちにインタビューを重ね、その重い胸の内を語ってもらった一冊。
【著者紹介】
【北川 敬一・著】 京都市出身。早稲田大学第一文学部人文学科、多摩芸術学園映画学科を経て、現在、映画、ドラマ、ドキュメンタリーなど映像全般の企画・制作・演出家として活動。自身も吃音者。日本工学院クリエイターズカレッジ非常勤講師。主な監督作品に、映画「鷲宮☆物語」、ドラマ「野ブタ。をプロデュ―ス」、ドキュメンタリー「GOOD-BY」、「空気」、「ただ、そばにいる」(第32回厚生労働省社会保障審議会推薦児童福祉文化財)など。
内容説明
親が子どもの吃音と向きあうための入門書。あなたのまわりに吃音の人がいたら、ぜひ、手にとってください。彼らの心の叫びがつまっています。
目次
第1章 小学生と中学生の親の気持ち
第2章 高校生と大学生の吃音の気持ち
第3章 社会人の吃音の気持ち
第4章 「吃音の気持ち」を話しあう
第5章 臨床と指導の現場から
第6章 吃音に向きあう、小学生と中学生のヒカル君の場合
著者等紹介
北川敬一[キタガワケイイチ]
京都市出身。早稲田大学第一文学部人文学科、多摩芸術学園映画学科を経て、現在、映画、ドラマ、ドキュメンタリーなど映像全般の企画・制作・演出家として活動。自身も吃音者。日本工学院クリエイターズカレッジ非常勤講師。主な監督作品に、「ただ、そばにいる」(第32回厚生労働省社会保障審議会推薦児童福祉文化財)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小木ハム
CCC
いちの
タラヲ
ちくわ