出版社内容情報
イネの先祖、遺跡から調べる、縄文時代、弥生時代、中世、太閤検地、篤農家たちの活躍、肥料の歴史、米騒動、休耕・転作等。
イネの先祖、遺跡から調べる、縄文時代、弥生時代、中世、太閤検地、篤農家たちの活躍、肥料の歴史、米騒動、米不足から米あまりの時代へ、明日につなぐ米づくり等。
目次
第1章 日本で米づくりが始まる―原始
第2章 米が主食となった―原始・古代
第3章 農村の文化が栄える―中世
第4章 米が国を支える時代―近世
第5章 新しい米づくりが始まる―近代
第6章 米不足から余る時代へ―戦後
第7章 明日につなぐ米づくり―現在
著者等紹介
常松浩史[ツネマツヒロシ]
1968年、佐賀県に生まれる。九州大学農学部卒業。大学でイネの遺伝学の研究を始める。1996年からフィリピンにある国際イネ研究所(IRRI)に勤務。IRRIでは、イネのいもち病抵抗性の研究に従事。2000年に農林水産省に入省。2001年より国際農林水産業研究センターから西アフリカ稲作開発協会(WARDA;現Africa Rice Center)へ派遣される。アフリカではコートジボアール、マリ、ナイジェリアに滞在。WARDAではアフリカでの陸稲の乾燥耐性の研究に従事
根本博[ネモトヒロシ]
1957年、福島県生まれ。宇都宮大学農学部卒業。農学博士。1981年に農林水産省に入省後、農業研究センター、熱帯農業研究センター、マレイシア農業開発研究所、茨城県農業総合センター、中国農業試験場、農研機構作物研究所等で水稲や陸稲の品種改良に関する研究に従事してきた。特に、水稲の多収性や害虫や病気への抵抗性の研究や陸稲の乾燥耐性を向上させる研究を行い、2000年頃からは牛や豚などのエサ用や米粉パンや米粉麺に利用するための水稲品種を開発するための研究に力を注いできた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。



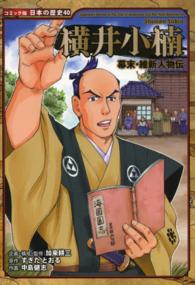
![基礎徹底マスター!フランス語練習ドリル 「CD+テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/41403/4140394692.jpg)



