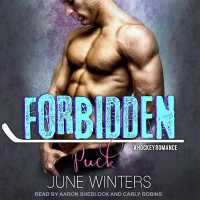- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
みそ、しょうゆ、酒等、和食の調味料の発酵に欠かせない存在、それがオリゼー。ふしぎなカビ、オリゼーをめぐる旅に出ましょう。
内容説明
和食に欠かせない調味料、みそ、しょうゆ、酒、みりん、酢。これらの調味料をつくるのに欠かせない存在、それが、世界で日本にしか存在しない微生物「アスペルギルス・オリゼー」です。千年以上前、日本人はこのオリゼーと出会いました。さあ、ふしぎなカビ、オリゼーをめぐる旅に出てみましょう。
目次
はじめに―微生物の星・地球
第1章 枯れ木に花を咲かせましょう
第2章 麹のスーパーパワー
第3章 伝統が途絶えようとするとき
第4章 もやし屋さんがいてくれる
第5章 オリゼーと気持ちは通じ合うか?―もやし屋さんの春夏秋冬
第6章 オリゼーをめぐるミステリー―オリゼーはどこからやってきた?
おわりに―春、ふたたび
著者等紹介
竹内早希子[タケウチサキコ]
神奈川県出身。ノンフィクションライター。大学卒業後、有機農産物宅配会社入社、主に品質管理部門で勤務。ドキュメンタリー映画製作スタッフ、NPOスタッフを経て執筆活動をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
千穂
35
今から1000年も前まだ顕微鏡もない時代に日本人は日本食の基本の調味料である味噌、醤油、酢、みりんを作る元となる麹菌、オリゼーに出会ったなんてすごいですね。その目に見えない生き物の存在に気づき大切に育てていたんですね。オリゼーを育てる専門家集団がもやし屋さん。リアルもやしもんの世界です。災害の多い日本で、お醤油やお酒の蔵が途絶えることなく再生出来たのももやし屋さんがいたから、なんて素晴らしいと思います。2020/11/05
seacalf
33
衝撃的。知らなかった。日本固有の麹菌、ニホンコウジカビとも呼ばれるアスペルギルス・オリゼー。日本人が千年以上も前から育ててきたオリゼーが味噌も醤油も日本酒も、みりん、お酢、塩麹や甘酒など日本の代表的な発酵食品すべてに関わっている。このオリゼーを取り扱ってきた世界で最も古いバイオテクノロジー技術集団、もやし屋さんは室町時代には既に存在していたという。顕微鏡が発明される遥か以前から一子相伝で連綿と現代まで受け継がれてきた。無知で恥ずかしいが驚くことばかり。知ってから口にする醤油も味噌汁も格別な味わいだ。2025/06/26
tom
16
読友さんのコメントで知る。著者名に既視感、確認すると「巨大なおけ」の著者だった。面白い本だった。この本では麹のことを書いている。私は、麹は単に麹と思っていた。でも、麹菌は味噌酒醤油を作るためにいろいろな人が使っていて、長い年月の間に、それぞれがちょっと違う性質を持つようになった。これが異なる風味、味などなどを生み出すのだ。そうでしたかと、ちょっとビックリする。そしてまた微妙に異なる麹を管理する「もやし屋」というお仕事もある。そうなんだ、知らぬこといっぱいあると喜んでしまった。2025/07/08
西澤 隆
9
顕微鏡が発明され菌が発酵に関与すると分かるよりずっと昔から麹を育て発酵のために供給する「もやし屋」が存在した日本。醤油や味噌や酒や、その他多くの発酵食品を支えるニホンコウジカビを通して発酵にせまる児童書は「もしその麹菌が喪われたら」という視点から東日本大震災や当地糸魚川の駅北火災のことも語る。ヒトがすべてのことをできるわけじゃない。大切にしてきた蔵のための麹菌にいい仕事をしてもらうために、ひとはご機嫌を伺い良い条件を整える。神頼みでもヒトだけの技術でもない協業。この距離感、子どもたちに伝わると、いいなあ。2018/11/09
あまね
8
図書館児童書コーナーで見つけたオリゼー(笑) 漫画のもやしもんとは直接関係なかったけど、日本食に欠かせない発酵の仕組みが丁寧に解説されてた良書。味噌、醤油、酒…私たちの食は眼に見えない微生物に支えられている。災害で蔵や設備を失っても、菌を保管してくれている「もやし屋」さんがいるお陰で、再び立ち上がることができた酒蔵や醤油屋。菌を「あの人」と呼ぶもやし屋の佐藤さんは、「菌が見える」というリアルもやしもん。千年かけて菌を育て継承してきた日本人のDNAには、確かに菌との幸せな協働が刷り込まれているのだろう。 2019/02/06
-
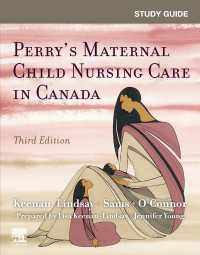
- 洋書電子書籍
- Study Guide for Per…
-

- 電子書籍
- 熟議のススメ