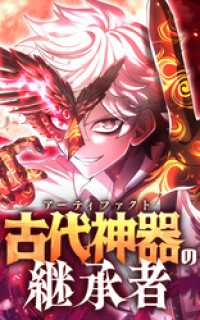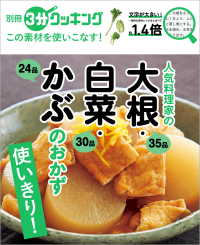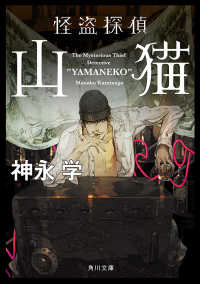出版社内容情報
思想家フェリックス・ガタリが終生関わったことで知られるラ・ボルド精神病院。世界中から取材者が集まるこの病院内を、一人の若い日本人女性が自由に撮影することが許された。彼女の震える眼が掬い取ったのは、患者とスタッフの間を流れる緩やかな時間。それは《フランスのべてるの家》ともいうべき、やさしい手触りを残す。ルポやドキュメンタリーとは一線を画した、ページをめくるたびに深呼吸ができる写真集です。
内容説明
世界中から取材者が集まるラ・ボルド精神病院の内部を、一人の日本人女性が撮影することを許された。やさしい手触りを残す患者とスタッフの間を流れる緩やかな時間。ルポやドキュメンタリーとは一線を画した、深呼吸ができる写真集。
著者等紹介
田村尚子[タムラナオコ]
写真家。1998年に初の個展を開催。以降、国内外での展示、活動を続ける。2010年には個展『ソローニュの森』を開催(タカ・イシイギャラリー京都)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。