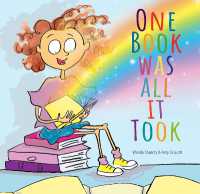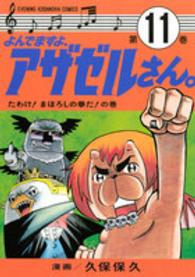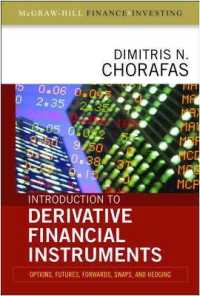内容説明
日本の伝統的な和食は、そもそも多品目をバランスよく摂取できる、すばらしい食事なのです。「一日の栄養所要量を満たしているか」「一日三〇品目摂れているか」などとあえて意識しなくても、日本人にふさわしい食べ物がふさわしい形で、過不足なく取り入れられるように、長い歴史のなかで培われ、受け継がれてきたのです。まるでパズルをとくように、和食と薬膳の伝統の知恵がわかる本。
目次
1章 和食は薬膳そのもの
2章 春の養生訓
3章 夏の養生訓
4章 土用の養生訓
5章 秋の養生訓
6章 冬の養生訓
7章 四季の一汁三菜
著者等紹介
武鈴子[タケリンコ]
1937年、鹿児島県生まれ。65~85年まで柳澤成人病研究所に勤務し、成人病と食生活の研究と指導に従事する。この経験から「食は薬なり」を実感し、食養の研究を始める。86年に薬膳研究のために訪中。四川省成都にて薬膳師・孫蓉燦氏に師事し、薬膳理論、料理技術を学ぶ。併行して東洋医学を日中医薬研究会会長・渡辺武博士に師事。日本の気候風土に合った薬膳理論を学ぶ。現在、東京薬膳研究所代表。食養研究家として講演、薬膳料理教室運営、健康食品開発などに携わっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
SAGA
6
季節と味と五行の関係から体にいい食べ方が語られてました。季節ごとに解説されていて読みやすい。レシピや食材と五味の表が載っていたので応用はしやすそうだ。旬のものはその季節に合っている食べ物だということがよくわかった。2011/06/10
ニーナ
1
旬には旬のものをやはり食べなくてはダメ・・・というより、体が受け付けなくなってきている気がして、薬膳や旬について知りたくて読みました。レシピも数種載っていますが、それよりも一般的な食材が何にあたるのか索引がついていたので、便利かもしれない。2011/10/03
yayanoa
0
五行説の観点から食養について、わかりやすく解説。久々に手元におきたい一冊に出会った。2014/10/07
dimsum
0
季節ごとに、体の様子とそれに合わせた食材が語られる。レシピも数種載っている。おもに、五行説。2011/08/21
ハリネズミ
0
すごく分かりやすかった。季節によってとるべき食味は知っていたが相生相剋の関係がよく分かっていなかったのでスッキリ。2018/03/31