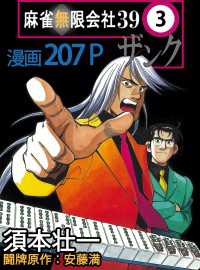出版社内容情報
日本は世界有数の森林資源保有国だった!
木の育て方、収穫、加工、流通、歴史、山村問題……
林業の基本と最新動向がよくわかる!
1.林業が注目されるわけ
森林が発揮する多様な機能/森林大国 日本/林業の特徴?農業とは異なる魅力? ほか
2.森林・樹木・木材を知る
世界の森林と砂漠化/日本の森林の特徴/変化する森林?植物遷移とは?? ほか
3.木を育てる林業を知る
日本の森林がもつ木材生産能力/持続可能な木材生産の考え方?保続生産とは?? ほか
4.木を使う林産業を知る
密接につながる林業と林産業/丸太から製材品へ/木材加工技術の現在 ほか
5.日本林業の歩み
体制とともに変容する林業?古代から近世? ほか
6.木材だけではない森からのめぐみ
非木材林産物生産(NWFP)とは何か?/キノコの生産と利用 ほか
7.林業のこれからを考える
各地で進む木材のブランド化の動き/林業の担い手を育てる取り組み ほか
関岡 東生[セキオカ ハルオ]
東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科教授。専門は、森林政策学、森林教育学、森林文化論。1965年、東京都生まれ。1995年、東京農業大学大学院農学研究科林学専攻修了。博士(林学)。日本森林学会・日本環境教育学会・日本野外教育学会・日本農業教育学会・林業経済学会他に所属。著書に、『日本の森林と林業』(大日本山林会、2011年)、『森林づくりの四季1・2』(上毛新聞社、2011年)、『木力検定?』(海青社、2014年)、『新版 森林総合科学用語辞典』(東京農大出版会、2015年)他。
内容説明
“森林国”日本の可能性と課題。林業と森林をめぐる基礎知識・最新動向がわかる。
目次
第1章 いま林業が注目されるわけ
第2章 森林と樹木を知る
第3章 林業を知る―樹木を育てる・収穫する
第4章 林産業を知る―木材を加工・消費する
第5章 日本林業と林政の歩み
第6章 木材だけではない森林からの恵み
第7章 これからの林業の可能性と課題を知る
著者等紹介
関岡東生[セキオカハルオ]
東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科教授。専門は、森林政策学、森林教育学、森林文化論。1965年、東京都生まれ。1995年、東京農業大学大学院農学研究科林学専攻修了。博士(林学)。日本森林学会・日本環境教育学会・日本野外教育学会・日本農業教育学会・林業経済学会他に所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
aisapia
乱読家 護る会支持!
桃の種
lovekorea
稲