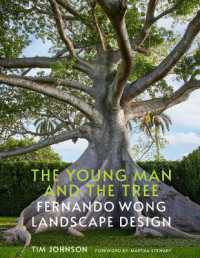- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
出版社内容情報
セザンヌの描く人物の不思議さが、こんなにも生き生きと語られたことがあっただろうか? 画家にとって上手い/下手とは? モダニズムがなぜ今要請されるのか? カントの命題を映画『マン・オン・ザ・ムーン』に重ね合わせ、ベンヤミンの思想を召喚して日本国憲法を論じる。マティス、デュシャン、ポロック、美術と世界、法と暴力……、稀有にして奔放、不羈にしてスリリングな対話は、浅田彰氏をして「この本を読まずしていま作品を制作し鑑賞することができると思う者は、よほどの天才でなければサルである」と言わしめた。
二〇〇二年セゾンアートプログラムから刊行され、大きな話題となった旧版はすでに絶版。今回、新規の対談五万字を第九章として増補した。新たに加えられた脚注は五百を数え、掲載図版は三百点に上る。全面的に著者の校閲を経た決定版。岡崎乾二郎装幀。
[本書を推薦します]
■浅田彰氏
ルネサンスから現代、西洋美術から日本美術に至る広い範囲にわたって、たえず具体的な作品に即して展開されるので、読者はつねに新鮮な発見に満ちた議論を追いながら、自ずと凡百の美術書をどれだけ読んでも得られぬ知見を得ることができるだろう。
■いとうせいこう氏
語られるべきすべての絵画の、言語形式での完全アーカイブ。このテキスト群はまるで百科全書のように一生涯参照可能だ。
■島田雅彦氏
芸術の歴史に深く思いを馳せながら、最初の原則に立ち戻るために言葉の限りを尽くしている。
●著者紹介●
松浦寿夫(まつうら・ひさお)
1954年、東京生まれ。画家、批評家。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。現在、東京外国語大学教授。西欧近代絵画の歴史/理論を研究すると同時に、絵画制作活動を続け、なびす画廊などで個展多数。編著として『シュポール/シュルファス』(水声社、1984年)、共同編著として『モダニズムのハード・コア:現代美術批評の地平』(太田出版、1995年)、共著として『モデルニテ3×3』(思潮社、1998年)、『村山知義とクルト・シュヴィッタース』(水声社、2005年)、共訳として、ティエリー・ド・デューヴ著『芸術の名において―デュシャン以後のカント/デュシャンによるカント―』(青土社、2001年)などがある。
岡崎乾二郎(おかざき・けんじろう)
1955年、東京生まれ。美術家。現在、近畿大学国際人文科学研究所教授。80年代よりパリ・ビエンナーレ、インド国際トリエンナーレなど数多くの国際展に出品し、2002年にはセゾン現代美術館にて大規模な個展を開催。同年に開催された「ヴェネツィア・ビエンナーレ第8回建築展」の日本館ディレクター、「灰塚アースワーク・プロジェクト」(1994-2003年)の企画制作、親水公園「日回り舞台」(2000年)の設計、美術評論など多彩な活動を展開。著書として『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房、2001年)、共著として『和英対峙 現代美術演習』(現代企画室、1989年)、絵本『れろれろくん』(小学館、2004年)、絵本『ぽぱーぺ ぽぴぱっぷ』(クレヨンハウス、2004年)、共同編著として『モダニズムのハードコア:現代美術批評の地平』(太田出版、1995年)、『漢字と建築』(INAX出版、2003年)などがある。
目次
純粋視覚の不可能性
代行性の零度
無関係性
「国民絵画」としての日本画
平面性の謎
誰がセザンヌを必要としているか
モダニズムの歴史という語義矛盾
メディウムと抵抗
著者等紹介
松浦寿夫[マツウラヒサオ]
1954年、東京生まれ。画家、批評家。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。東京外国語大学教授。西欧近代絵画の歴史/理論を研究すると同時に、絵画制作活動を続け、なびす画廊などで個展多数
岡崎乾二郎[オカザキケンジロウ]
1955年、東京生まれ。美術家。近畿大学国際人文科学研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kentaro
yu-onore
なっぢ@断捨離実行中
toshibowdayo
seek
-
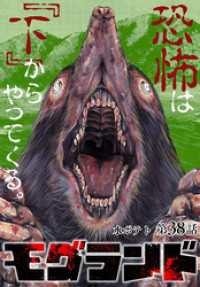
- 電子書籍
- モグランド 分冊版 第38話 ゼノンコ…
-
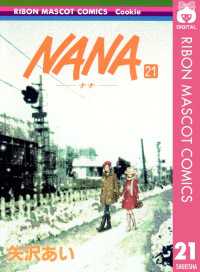
- 電子書籍
- NANA―ナナ― 21 りぼんマスコッ…