- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
内容説明
アートは、より頭脳的に進化する。もはや“アート”は、“芸術”ではない。では、今のアートは、何を表現しているのか。内外の最新の動向を踏まえ、21世紀のアートの新しい見取り図を明晰に語る。
目次
第1章 モダンからポストモダンへ―「芸術が終わったあとの芸術」の始まり
第2章 表象批判からファンタジーへ―変貌するポストモダン芸術
第3章 リアルなものの探究―「おぞましい」身体、文化多元主義、はかなさの力
第4章 美と日常性の再発見
第5章 「モダニズム」の閉じゆくフィールド、立ち現れる「現代の美術」
著者等紹介
松井みどり[マツイミドリ]
上智大学、東京大学大学院で英米文学、プリンストン大学大学院博士課程で比較文学を専攻。1994~95年頃から海外の学術誌、論文集、企画展カタログに同時代の日本の現代美術の潮流や作家について論文を寄稿している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
43
美術表現の多様化とそれに対する絶対的な価値基準の欠如に対して「美術の終わり」(the end of art)と表現された1960年代から現在までの美術の状況を分析するカルチャー・スタディーズの1冊。モダンからポストモダン、表象批判からファンタジーへ、文化多元主義アートなど80年代、90年代に現れた美術表現の傾向を振り返り論じているので、「美術の終わり」の後の現代美術のおおまかな流れが把握できる。2014/08/12
zirou1984
40
80~90年代にかけてのアートの潮流を抑えた良書。本当は入門書と言いたい所だけど、この時期のアートの理論的土台は現代思想の概念に拠る部分が多いため、その辺りについて詳しくないと難しいかもしれない。現代アートは自身が批評的まなざしを内包し、その批評性が問われるため真善美という旧来の芸術における価値基準が2次的問題となっていくのが大きな特徴と言えるだろう。その批評性はまた反動と次なる批評を生み出してゆく訳で、現代アートとは体系付けられた時点で過去のものとなってしまう刹那性から逃れられないものなのかもしれない。2014/07/12
しゅん
16
モダニズム以降の現代アート入門書。美術が形而上学的基盤を失った後に、政治的作用を及ぼすことを主眼とする「アート」へ変容していった。その後の展開を時代を追いながら閲覧していく。作家とあわせて批評家、キュレーターの動向も追っている分、アートの世界全体の概要が見て取れるので、美術をめぐる思想の整理にとても役立つ。個人的にはティルマンスやペイトンなど、好きな作家のアート界でのある程度の立ち位置(前者の「日常性の肯定」後者の「キッチュの昇華」)を知ることが出来て、美術を思考する楽しみが広がった。2017/09/21
ooo
12
現代美術の教科書として、多くの美術関係者が手にする本。「この本を何度も何度も読み返して、現在へ続く一連の流れを抑えた。」という話を、色んなところで耳にするような、そんな定評のある一冊です。題名にもなっている「"芸術"が終わった後の"アート"」とは、哲学者アーサー・C・ダントーの言葉。抽象表現主義に代表される、それまでの形態中心の美術(モダニズム)を否定し、コンセプトを重視のポストモダニズム芸術を示す言葉として使われています。膨大な量の情報が、明確且つ簡潔な言葉で語られる。2014/08/13
sakanarui2
6
1980年〜2000年の、アメリカを中心とした現代美術の潮流、その変容について書かれた本。代表的な作家や作品、アート界の転機となった出来事を振り返りつつ、アーサー・C・ダントーなど現代美術について論じた思想家や批評家の言説を批判的に検討する。 アートの価値基準は大きく変化し混沌としていて、美術館や批評の役割も定義しにくい状況。アートがSNSでシェアされる存在となったいま、それを全面的に歓迎すべきなのかどうかはわからないが、少なくともアートがより身近で人々に開かれたものになってはいると思った。2024/08/02
-
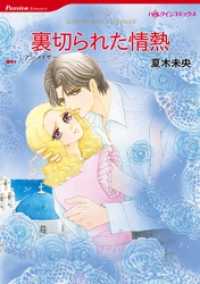
- 電子書籍
- 裏切られた情熱【分冊】 8巻 ハーレク…
-

- DVD
- 覇者の掟 第三章






