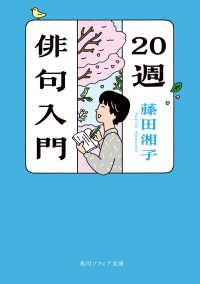出版社内容情報
方言の実態と原理,音韻,アクセント,文法,語彙と比喩,表現,全国の分布等,研究成果を論述方言の全体像を解明し研究成果を論述。〔内容〕方言の実態と原理/方言の音韻/方言のアクセント/方言の文法/方言の語彙と比喩/方言の表現,会話/全国方言の分布/東西方言の接点/琉球方言/方言の習得と共通語の獲得/方言の歴史/他
第1章 方言の実態と原理
1.1 方言の成立
1.2 方言の地理的側面(歴史的視点)
1.3 方言の社会的側面(共時的視点)
1.4 方言の認識的側面(価値的視点)
1.5 方言の原理
第2章 日本方言の音韻
2.1 /'i/と/'e/について
2.2 /0'e//0'i/
2.3 後中子音鼻音化現象・有声化現象
2.4 「火事」の/kwa/の分布と「鍬」の変容
2.5 今後研究が望まれる音現象の例
2.6 (社会的)高次共時言語学と構造的高次共時言語学,そして構造・
社会的・心理的高次共時言語学的研究へ
2.7 今後望まれるデータ提示の方法
第3章 方言のアクセント
3.1 アクセント体系の考え方
3.2 語アクセントと句音調
3.3 名詞に接続する助詞・助動詞のアクセント
3.4 動詞に接続する助詞・助動詞
3.5 複合語のアクセント
3.6 アクセントの分布と変遷
3.7 アクセント研究の課題
第4章 方言の文法
4.1 方言文法の比較・対照
4.2 方言文法の古態性・改新性と地理的分布
4.3 共通語の干渉による方言文法の変容
第5章 方言の語彙と比喩
5.1 方言語彙研究の概観
5.2 方言語彙の変容
5.3 方言の比喩
5.4 対照方言語彙論
5.5 方言語彙研究の課題
第6章 方言の表現・会話(談話)
6.1 談話研究の必要性
6.2 談話研究に見られる3つの方向
6.3 談話資料の実際
6.4 談話研究の課題
第7章 全国方言の分布
7.1 方言の分布
7.2 分布とは何か
7.3 分布と分布パタン
7.4 分布の定式化
7.5 分布パタンの定式化について
7.6 全国的データに関する基礎資料
7.7 分布類型と分布パタン類型
7.8 リング?型・波紋?型(P)
7.9 リング?型・波紋?型(P)
7.10 東西A型(P)
7.11 東西B型(P)
第8章 東西方言の接点,
8.1 いわゆる「東西方言の境界」の発見とその意味
8.2 東西方言の対立的言語事項
8.3 東西対立事項にひそむ問題
8.4 東西接点の具体相
第9章 琉球の方言
9.1 九州方言との関係
9.2 琉球方言の下位区分
9.3 文法の観点からみた琉球方言
9.4 ウチナーヤマトゥグチ
第10章 方言の習得
10.1 子どもたちの言語獲得とコミュニケーションの場との関係
10.2 家庭(子どもたちが言語を習得する場1)
10.3 友人・仲間(子どもたちが言語を習得する場2)
10.4 学校?わきまえことば?(子どもたちが言語を習得する場3)
10.5 地域社会?方言の習得とその変容?(子どもたちが言語を習得する場4)
第11章 方言のデータベースとコンピュータ言語地図
11.1 方言のデータベースを取り巻く環境
11.2 理想のデータベースとは?
11.3 パソコンを用いた方言地図の作り方(概要)
11.4 パソコンを用いた方言地図の作り方(詳細)
11.5 データベース公開の方法
第12章 日本語方言の歴史
12.1 方言史の考え方
12.2 方言史の方法論
12.3 格助詞サの歴史―方言形式の成立
12.4 動詞活用の歴史―言語体系の変遷
12.5 残された課題
第13章 方言研究の歴史
13.1 全体の流れ
13.2 方言区画論
13.3 言語地理学
13.4 比較方言学
13.5 記述的研究
13.6 社会言語学的研究
14.索引
北原保雄[キタハラヤスオ]
監修
江端義夫[エバタヨシオ]
編集
目次
方言の実態と原理
日本方言の音韻
方言のアクセント
方言の文法
方言の語彙と比喩
方言の表現・会話(談話)
全国方言の分布
東西方言の接点
琉球の方言
方言の習得
方言のデータベースとコンピュータ言語地図
日本語方言の歴史
方言研究の歴史
著者等紹介
北原保雄[キタハラヤスオ]
1936年新潟県に生まれる。1968年東京教育大学大学院文学研究科博士課程退学。前筑波大学長、日本学生支援機構理事長。文学博士
江端義夫[エバタヨシオ]
1943年愛知県に生まれる。1969年広島大学大学院文学研究科修士課程修了。広島大学大学院教育学研究科教授。文学修士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- ともにゃんにゃんの大冒険