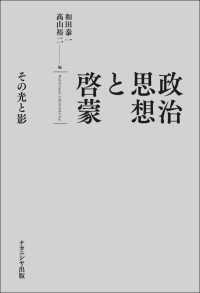出版社内容情報
神話の原典となる資料・文献の研究史を土台にして,世界各地の神話と神話学の展開を学ぶ。
山田仁史[ヤマダ ヒトシ]
東北大
目次
聖書という前提―ユダヤ=キリスト教世界
古典古代の遺産―ギリシャとローマ
新世界との出会い―南北アメリカ大陸
『エッダ』と『オシアン』の衝撃―ゲルマンとケルト
比較言語学から宗教学・神話学へ―ペルシャとインド
ロゼッタストーンとギルガメシュ―エジプトとメソポタミア
南海の魅惑―オセアニア
翻訳された日本・琉球・アイヌの神話
新大陸との再会―マヤ・アステカ・インカ
フェティッシュとシャマン―アフリカと北ユーラシア
宣教と民俗誌―東南アジア
シノロジーから東アジア学へ―中国と朝鮮半島
著者等紹介
山田仁史[ヤマダヒトシ]
1972年宮城県に生まれる。1995年東北大学文学部卒業。2003年京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程満期退学。ミュンヘン大学大学院修了。現在、東北大学大学院文学研究科准教授。Dr.phil.(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白狐
11
レポート用として読んだ本。地域別に書かれていて、どの神話なのかが分かりやすかった。聖書や古事記、日本書紀、エジプト神話ギリシャ神話くらいしか知らなかったので、他の地域の神話が書かれていたのは嬉しかった。オセアニアについては初めて知った。今度どこかの神話でも読みたい。2017/11/24
ぺったらぺたら子
5
良い本。世界各国の神話をヨーロッパを定点にして、つまりヨーロッパが発見・受容していく順に整理していく、というアプローチが良くて、個々の記述は少ないものの、世界史的に見渡せるという点で入門として素晴らしい。たとえば何故ゲーテはウェルテルの後半をオシアンで埋め尽くしたのかの意味も解った(この本に直接説明されているわけではないですが)。フランス啓蒙主義に対するドイツロマン主義、とか。ナチスが神話やワーグナーを利用した、その歴史的な流れ、とか。入門くらいで私には丁度良いです。2017/08/04
うえ
3
聖書からエッダ、アステカまで網羅した神話学入門。「宗教や神話同士の比較も始まった…中で登場した近代神話学・宗教学の祖として知られるのが、フリードリヒ・マックス・ミュラーだ。ドイツ生まれだが…オックスフォードのドイツ人として過ごした。その専門はもとは言語学、ことにサンスクリットだった。…ミュラーは、学問分野の名称として「宗教学」という言葉を初めて用いた…1867年に刊行された著書のタイトルとして使用している。その比較神話学の最初のマニフェストと言えるのが、1856年に出た「比較神話学」という論文であった。」2023/10/09
catfist
3
聖書に毒されてる感が強い。神話学者が聖書を軸にしているから、というなら学説史とすべきではないか。オリエンタリズムが気分も漂い、神話学全体を見通そうという気概は感じ取れない。2020/11/23
ヌンヌ
1
とてもおもしろい。地域ごとに書かれているけど、繋がっているところもたくさんある。ギリシャ神話があまりに有名だけど、ドイツ神話も美しい響きが素敵だし、東南アジア系も面白いね。おかげで神話学再熱した。あと猿亀合戦割と好き。2017/08/08