出版社内容情報
豊富なカラー図版を用いて流れを可視化する方法と実際を解説。〔内容〕可視化とその歴史/流れと可視化(流れの性質,可視化の実際,可視化情報の理解,可視化の効用)/可視化記録と機器(写真の撮り方,ビデオの撮り方,特殊な記録法)/付録
【目次】
1. 可視化とその歴史
1.1 可視化のはじまり
1.2 可視化を育てた人々
1.3 可視化の国内および国際情勢
1.4 可視化の利用
1.5 可視化の将来展望
2. 流れと可視化
2.1 流れの性質
2.5 可視化の実際
2.3 可視化情報の理解
3. 可視化記録と機器
3.1 写真の撮り方
3.2 ビデオの撮り方
3.3 特殊な記録法
4. 付 録
4.1 ディジタルスチールカメラの例
4.2 スチールカメラ一覧
4.3 ビデオカメラ一覧
5. 索 引
【編集】
可視化情報学会
【編集委員】
青 木 克 巳, 植 村 知 正
川 崎 正 昭, 小 林 敏 雄
高 木 通 俊, 中 山 泰 喜
内容説明
第1章では「可視化の歴史と現状」について述べることにしました。可視化の源をたずねますとはるか縄文時代にまでさかのぼっていくように思います。そこで、縄文土器に見られる美しい渦模様から考察を始めて、近代科学の眼を通して古代文化に学びつつ、約5000年の昔に夢を馳せていただくことにいたしました。ついで、近世に戻って、実際に可視化技術を利用して近代科学の発展に貢献した6人の方を選び、その業績をエピソードを含めて、興味深く記述してみました。最後に可視化の利用の現状について概要が述べてあります。第2章では「流れと可視化」というタイトルで、まず流体の力学の基礎について解りやすく解説してあります。ついで、可視化の実際として、いろいろの現象について、可視化写真を眺めつつ、現象をどのように理解していくかを懇切丁寧に説明してあります。最後に、実際に可視化するにあたって、注意すべき事柄が述べてあります。第3章「可視化記録と機器」では、まず“写真の撮り方”として、撮影条件の整備、撮影機器と材料、撮影の実際、撮影後の処理について説明され、つぎに“ビデオの撮り方”として、ビデオ制作の概要、撮影機器、撮影、撮影条件の整備、編集、編集装置について説明され、最後に“特殊な記録法”として、高速度カメラの解説、これを使った流れの可視化応用例、高速度撮影の実際、赤外線・紫外線の記録などにわたって詳細に述べられています。なお、実際に利用されるのに便利なように、巻末に現在市販されているカメラ、ビデオの一覧表の掲載しておきました。
目次
1 可視化とその歴史
2 流れと可視化
3 可視化記録と機器
-
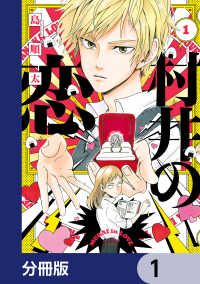
- 電子書籍
- 村井の恋【分冊版】 1 ジーンLINE…

![山下和仁/山下和仁の芸術[4]ギター協奏曲集](../images/goods/ar/web/vimgdata/4547366/4547366537215.jpg)




