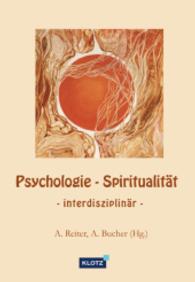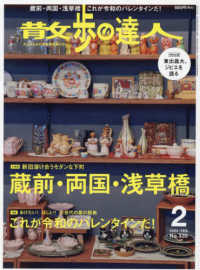内容説明
「ハビトゥス」「象徴暴力」「文化資本」…。難解にして深遠なP・ブルデューの世界。その基盤、方法、論理、そして今日的意義を平易に解説。格好の入門書。
目次
第1章 社会科学の認識論
第2章 ブルデュー社会学の方法と基本概念
第3章 ブルデュー社会学における構造と主体
第4章 ブルデュー社会学における実践の論理
第5章 ブルデューにおける支配の論理
第6章 ブルデュー社会学における階級論
第7章 ブルデュー社会学とマルクス理論
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イリエ
7
解説書なのに、こんなに難解で大丈夫か、と心配してしまうくらいの本でした。意味もわからず、20ページほど進んでしまうこともざらにありました。ただ、社会的な行為のリアリティを復権しようとしたのはわかった、気がします。自分のしていること、立場がスっと崩れる感覚がありました。「構造は、『人間的主体性』を受け付けないものであり、『行為者を賢明にプログラムされた自動人形にしてしまう』のである」2017/10/03
ぽん教授(非実在系)
4
ピエール・ブルデューがまだ生きていて反新自由主義運動をしていたころに書かれたもの。バシュラールやカンギレームなどの「対科学への認識論」をベースにしながら、マルクス・ウェーバー・デュルケムのダメなところを切り捨て良いところを総合し、直観と実証どっちもできなければいけないとする中でたどり着いたのは、移動する床みたいなものとしてのハビトゥスである。社会構造に基づいて人は流されるものの、あえて逆らって動くこともできなくもない、単なる決定論ではないものとして社会学をデザインしているのである。2017/01/23