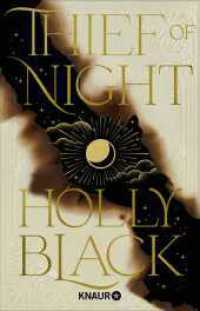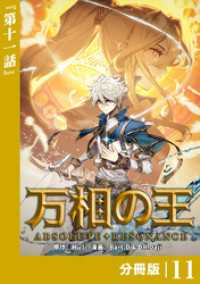内容説明
大量餓死をもたらした日本軍の責任と特質を明らかにして、そのことを歴史に残す。そして、そのことを死者に代わって告発する。
目次
第1章 餓死の実態(ガダルカナル島の戦い;ポートモレスビー攻略戦 ほか)
第2章 何が大量餓死をもたらしたのか(補給無視の作戦計画;兵站軽視の作戦指導 ほか)
第3章 日本軍隊の特質(精神主義への過信;兵士の人権 ほか)
著者等紹介
藤原彰[フジワラアキラ]
1922年東京に生まれる。1949年東京大学文学部史学科卒業。現在、一橋大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
29
様々な書籍で、戦地での飢餓を読んできました。けれどもこのストレートなタイトルの本に記された膨大な数字(諸説あるようですが)、逸話にただ悲しみを覚えました。先日ファストフードとMRE(戦闘糧食)の歴史について書かれた本を読み、エネルギーの確保を現地任せにしないアメリカの徹底した研究っぷりにびっくりしましたが、精神論を説き、現実を見失った上司に苦労させられる部下…という絵図は日本では変わってない気がして怖いです。2019/01/12
モリータ
11
第1章は大量の餓死・病死者を出した各戦線(ガダルカナル、ニューギニア、ビルマ、フィリピン)+中国での実態の紹介、第2章は補給軽視、精神主義、エリート教育といった一種常識となった陸軍の欠陥について述べられる。入門書には良いと思うが、各戦線で兵站・補給が無視された作戦が行われたのはなぜか、純粋に峻険な地形や島嶼部での戦争のノウハウがなかったのか、大戦初期に兵に食わせずとも勝てたような事例が正のフィードバックとして効いていたのではないかとか、そのあたりをもっと知りたかった。辻・服部が跋扈できた理由とも絡む気が。2017/08/22
ゆきのん
7
2001年発行。もっと早くに読むべきだった。このような事実を知れば知るほど、「顕彰」から「慰霊」へと考え方がシフトしてくる。餓死した兵士も気の毒だが、馬は1頭も帰ってこれなかったと。軍の上層部は人も馬も物扱いしていた。上に立つ人は頭がいいだけじゃダメだな。今の政治家にも言えるけど、国民を将棋の駒のように扱っている。捕虜になることが認められていたら、あと1年、半年でも早く戦争が終わっていたら、と思わずにはいられない。2019/01/26
shushu
7
中国戦線に従軍した研究者が明らかにする第二次世界大戦の日本軍の実態。日本人の戦没者は310万人、内軍人軍属の死者数は230万人とされている。その過半数は餓死、戦病死であり、戦闘死ではない。こういう本を読んでいると、日本に戦争をする能力がなかったと思うし、日本の戦いはアジアの独立に役立ったという一部の意見がいかにデタラメか、また日清戦争では戦陣衛生の配慮を欠き、日露戦争では装備不足により多くの戦死を招いた、ことは、これまでの明治はまともだった、というイメージが間違っていたことがわかる。また、馬を徴用し、2018/07/11
godon
7
軍の資料から引っ張ってきて、大戦末期における日本軍の餓死の実態を詳しくかつ生々しく書いた本。現地自活で何とかせいや、と地図も殆どないような島へ軍を送って餓死させる等、大本営の無能な精神主義を強く糾弾(わりと名指しで!)している。この手の批判は方々でなされていて新鮮味はないが、どの隊がどのように窮して大量餓死したか(あるいは糧食に窮してバンザイ突撃したか)ということが詳しく書かれているのが非常に良かった。美化された戦死のイメージしか持ち合わせていない人にとっては、認識を改めるきっかけになろうかと思う。2013/07/27