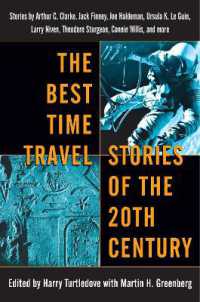出版社内容情報
ひとつひとつちがう、島の地形を見てみよう! 「水」を切り口に日本の地形をさぐる、シリーズ第三弾。
まわりを海にかこまれた国、日本は、4つの大きな島(本州、北海道、四国、九州)と、6800以上の小さな島々からなる島国。島は、ぷかぷかと海に浮いているのはありません。海底にそびえたつ山のてっぺんが水面から出たものが、島なのです。島の地形には、ひとつひとつ特徴があります。海水にかくれた部分もふくめて島を理解することで、島の地形がよく見えてくるでしょう。「水」を切り口に、日本の地形をさぐるシリーズ第3巻。
【著者紹介】
鹿児島大学国際島嶼研究センター。日本島嶼学会会長。島の専門家。監修を担当した本に『世界の島大研究』(PHP研究所)など。
内容説明
まわりを海にかこまれた国、日本は、6800以上の島々からなる島国。これらの島は、ぷかぷかと海に浮いているのではありません。海底にそびえたつ山のてっぺんが水面から出たものが、島なのです。本書では、水にかくれた部分もふくめて、島の地形をくわしく探っていきます。「水のある場所」に注目して、世界最大規模の地図データを駆使し、ビジュアルにわかりやすく地形を解説するシリーズ第3弾。小学校中・高学年~
目次
第1章 北海道・日本海北部の島々(海のめぐみ豊かな北の島々―北海道・千島列島;北海道の北部、日本海にある2つの島―利尻島・礼文島(北海道) ほか)
第2章 伊豆・小笠原の島々(海底火山がつくった島々―伊豆諸島・小笠原諸島;噴火をくり返す海底火山の島―伊豆大島(東京都) ほか)
第3章 中四国・九州北部の島々(大陸との交通路になった島々―瀬戸内海・九州北部の島々;日本海にある険しい火山の島々―隠岐諸島(島根県) ほか)
第4章 九州南部・南西諸島の島々(サンゴ礁が広がる亜熱帯の島々―南西諸島;海底が隆起してできた2つの島―屋久島・種子島(鹿児島県) ほか)
著者等紹介
長嶋俊介[ナガシマシュンスケ]
1949年、新潟県佐渡島生まれ。前鹿児島大学国際島嶼教育研究センター教授。京都大学、会計検査院を経て、奈良女子大学教授就任後、瀬戸内海・豊島の産業廃棄物問題を側面から支える活動も展開。日本島嶼学会を設立、副会長・事務局長を経て現在、会長。国際島嶼学会理事もつとめた。専門は、生活経営学、生活環境学、比較島嶼論、島嶼学原論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shiho♪
Hiroki Nishizumi