内容説明
崩壊に向かう世界経済、500年に一度の大変動に我々は何をなすべきか?ユーロ危機、財政破綻、貧困の蔓延、原発事故…「西洋からアジアへ」。迫り来る大転換に向けて日本の進むべき道を示す。
目次
第1章 資本主義はやはり「自壊した」のか
第2章 資本主義はいかにして発展し、衰退したのか
第3章 「失われた二〇年」で日本はなにを失ったのか
第4章 中国の“資本主義”をどう理解すべきか
第5章 最高の社会資本としての「信頼」
第6章 「資本主義以後」の日本企業
第7章 戦略的・脱原発政策のすすめ
第8章 日本は「文明の転換」を主導できるか
著者等紹介
中谷巌[ナカタニイワオ]
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)理事長。一般社団法人「不識庵」理事長。「不識塾」塾長。一橋大学名誉教授。多摩大学名誉学長。42年1月22日大阪生まれ。65年一橋大学経済学部卒。日産自動車に勤務後、ハーバード大学に留学。73年、ハーバード大学経済学博士(Ph.D)。その後、同大学研究員、大阪大学教授、一橋大学教授、多摩大学学長を歴任。細川内閣の「経済改革研究会」委員、小渕内閣の「経済戦略会議」議長代理を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
稲岡慶郎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
だいすけ
18
「資本主義はなぜ自壊したのか」と論点は同じだが、分厚い中間層の大切さなどがよくわかる。ジャックアタリが指摘するように、にっちもさっちもいかなくなる前に発想の転換が重要だ。かつて、日本が大切にしていた価値観や文明を軸に世界を主導できるかが問われている。また、読んでいて感じたことは現在の自分の働き方が、かつて西欧諸国が非西欧諸国を収奪したやり方に似ているということだった。例えば、激安の食品を買ってそれを労働力に変えて、会社にその労働力を提供して対価を得ることなど。本書が主張する共存共栄の考え方とは違う気がする2018/01/10
tetsu
16
★5 世界の歴史や宗教をこうゆう観点で学べると興味が湧き身につく気がします。 理想と現実のはざまを模索してゆくような視点で書かれている印象を受けました。中谷巌、他の著書も読んでみたくなる。2019/04/07
Miyoshi Hirotaka
13
激動の時代という枕詞をよく耳にする。ところが、町人文化が花開いた江戸時代にも赤穂浪士は討ち入りをし、大塩平八郎は乱を起こし、伊能忠敬は日本地図を作った。あらゆる時代は無常。その中で目先のことに流されず、大局観を持つことが必要。ところが、これには万巻の書を読むという努力が必要。しかし、その結果として実行すべきことは驚くほど簡単なことばかりだ。「着眼大局、着手小局」。幸いにもわが国には見習うべき先例が豊富にある。視聴率稼ぎのTVのコメンテーターに惑わされることなく、知と正面から向き合うことが必要だ。2013/05/25
マカロニ マカロン
12
個人の感想です:B+。本の表題から、グローバル資本主義以降の世界はどうなるのかを書いてあるのかと思ったが、内容の大半はサブタイトルの「日本は「文明の転換」を主導できるか」に充てられている。大震災以降の日本の針路に対する提言だが、民主党政権下の2012年発行なので既に古い部分もある。日本人の「自虐史観」に批判的だが、そのために「陰謀史観」的な主張も多い。その部分はあまり賛成できないが、核抑止力のため原発を2、3基だけ国有化して保有し、主なエネルギー源は再生可能なものに変更していくという提言は賛成だ。2015/10/29
れう
6
大航海時代から始まる資本主義の歴史と、その行き詰まりには納得。本書の言うように、何らかの「文明の転換」が必要なのだろうが、難しいよね〜2014/01/23
-
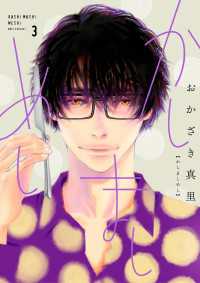
- 電子書籍
- かしましめし(3)【電子限定特典付】 …
-
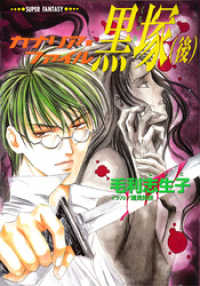
- 電子書籍
- カナリア・ファイル 黒塚(後)(スーパ…
-
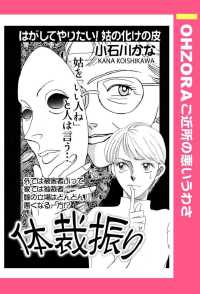
- 電子書籍
- 体裁振り 【単話売】 - 本編 OHZ…
-
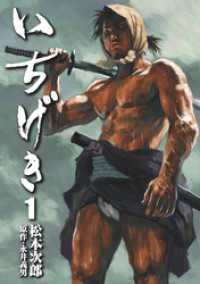
- 電子書籍
- いちげき (1) SPコミックス
-
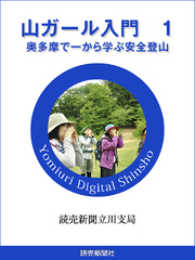
- 電子書籍
- 山ガール入門 1 読売デジタル新書




